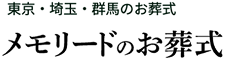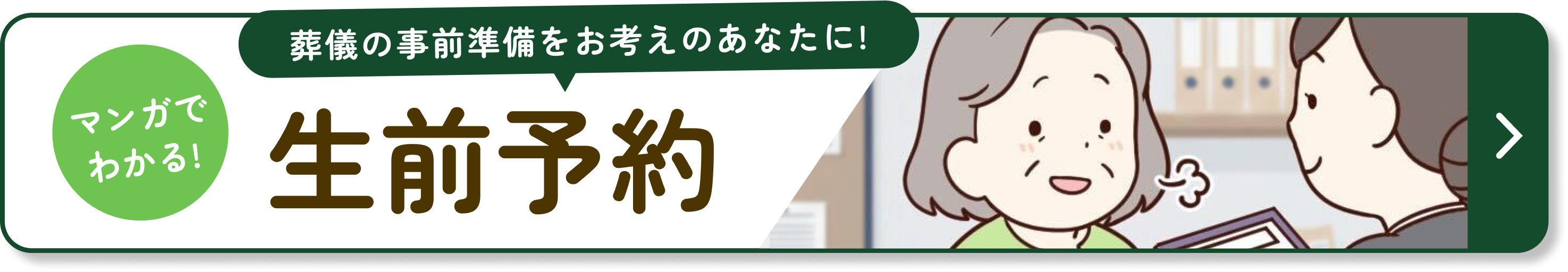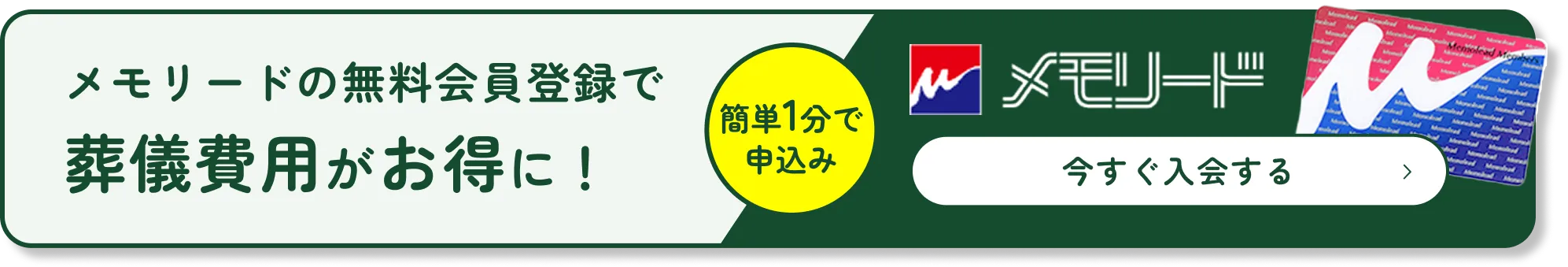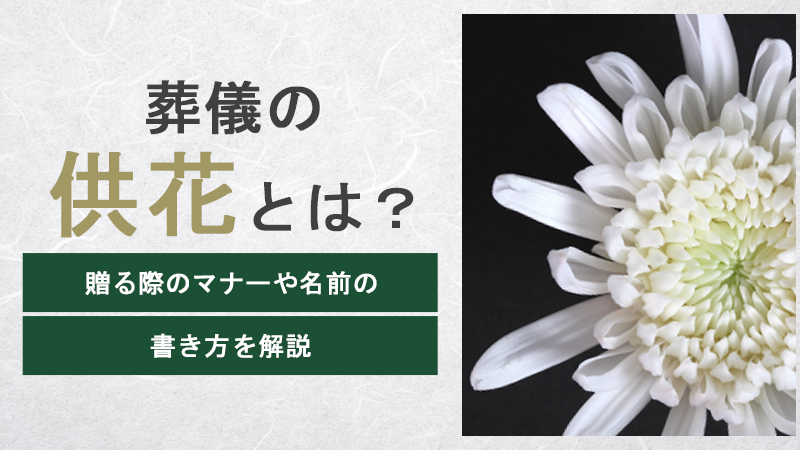葬儀に供花を贈る際「どのような花を選べばよいのか」「どのタイミングで届くように手配すればよいのか」と悩まれる方は少なくありません。さらに、宗教によるマナーの違いや、供花と香典の使い分けに戸惑うケースも多く見受けられます。
こうした不安や疑問を解消するために、本記事では供花の種類・相場・贈る際の注意点をはじめ、手配の方法や札名の書き方まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。故人への哀悼の意と、遺族への思いやりをしっかりと伝えたいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
葬儀で贈る供花とは?
葬儀で贈る供花は、故人への哀悼の意と遺族への心遣いを表す大切なものです。たとえば会社関係では「○○株式会社一同」などでスタンド花を贈るのが一般的で、個人の場合も関係性に応じた花の選び方が求められます。
とくに日本では宗教や地域によって習慣が異なるため、基本的なスタイルや数え方を理解しておくことが大切です。それぞれ詳しく解説していきます。
基本スタイル
供花には大きく分けて「スタンド花」と「アレンジメント」の2種類があり、それぞれ使用される場面や意味合いが異なります。スタンド花は、祭壇の左右に一対で飾られることが多く、見た目にも華やかで存在感があるため、会社や団体からの贈り物としてよく選ばれます。
「株式会社○○ 代表取締役 △△」といった名札を添えて贈るのが一般的です。一方で、アレンジメントは籠花や花束などが中心で、受付や控室、自宅への弔問の際などに用いられることが多く、親族や友人など個人から贈る場合に適しています。
供花の費用は、1基あたり7,500円〜15,000円程度が一般的な相場となり、1対で贈る場合にはその2倍、つまり15,000円〜30,000円ほどになりますが、とくに選ばれることが多いのは2万円前後の供花です。なお、宗派や地域によって、使用する花の種類や色に好みがある場合もあるため、事前に遺族や葬儀社へ確認しておくと安心です。
供花は単なる形式ではなく、故人やご遺族への心を込めた贈り物であるため、大切な気持ちをきちんと伝えるためにも、慎重に選びましょう。
数え方
供花を数える際には「一対(いっつい)」または「一基(いっき)」という数え方が用いられます。一対は左右対で2本一組の供花を意味し、より丁寧な贈り方とされています。
たとえば、親族や会社関係で供花を出す場合、一対で贈るのが一般的です。一基は1本のみを指し、個人や友人などで気持ちを込めて贈るときに選ばれることが多いです。
葬儀会場のスペースや祭壇のバランスを考慮し、会場側から「一基のみ」と指定されることもあるため、事前に確認しておきましょう。
供花の種類
葬儀で贈る供花は、故人が信仰していた宗教や葬儀の形式によって適切な種類が異なります。間違った供花を贈ってしまうと失礼にあたることもあるため、事前に葬儀の形式を確認することが大切です。
・仏式の場合:白や黄色の菊が中心
・神式の場合:白い花が基本
・キリスト教式の場合:ユリなどの洋花が一般的
それぞれの宗教や宗派に合わせた適切な供花を選ぶことで、故人への敬意を正しく表せます。ここでは、各宗教における供花の特徴について詳しく解説します。
仏式の場合
仏式の葬儀では、白を基調とした落ち着いた花が一般的に選ばれます。なかでもよく使われるのが以下のお花です。
・白菊
・白ユリ
・白いカーネーション
これらの花にはそれぞれ「誠実さ」「清らかさ」「無垢」といった意味があり、故人への哀悼や敬意を表すのにふさわしいとされています。供花としては、これらの花を使ったスタンドタイプが主流で、祭壇の左右に一対で飾られるケースが多く見られます。
ただし、宗派や地域によっては花の種類や飾り方に違いがあるため、事前に葬儀社や遺族に確認しておくのが安心です。仏式の供花は見た目の華やかさよりも、亡くなった方への感謝や想いを伝えることが大切にされます。
そうした気持ちを込めて花を選ぶようにしましょう。
神式の場合
神式の葬儀で用いられる供花は、基本的には仏式と同様に白を基調とした落ち着いた色合いの花が選ばれます。白ユリやカスミソウ、カーネーションなどがよく用いられ、清らかさや慎ましさを表現するデザインが好まれます。
飾り方も仏式と同じく、祭壇の左右に一対で並べるのが一般的です。ただし、神式には特有のしきたりもあり、供花に加えて「神饌物(しんせんぶつ)」と呼ばれるお供え物を用意することがあります。
塩、米、季節の果物や野菜などを霊前に供えることで、故人の御霊に敬意を表します。このように、供花のスタイルは仏式と大きく変わりませんが、神式ならではのマナーもあるため、葬儀社や神社に確認しながら準備することが大切です。
キリスト教式の場合
キリスト教式の葬儀では、白を基調とした洋花のアレンジメントが供花としてよく用いられます。ユリやカーネーション、トルコキキョウ、白いバラなどを組み合わせた清楚で上品なデザインが選ばれ、故人への祈りや敬意を込めて手向けられることが多いです。
カトリックとプロテスタントの間には細かな違いがあるものの、いずれも派手な装飾は避けられ、シンプルで落ち着いた雰囲気の花が好まれます。とくに十字架が飾られることの多い会場では、空間全体とのバランスを考えた花選びが求められるでしょう。
また、仏式では通夜や葬儀会場へ直接供花を届けるケースが一般的ですが、キリスト教式では、故人のご自宅へ小ぶりなバスケットフラワーを贈る形式が主流となっています。
供花以外に贈る花の種類
葬儀においては、供花のほかにも故人を偲ぶために贈る花があります。それぞれに意味や役割が異なるため、目的に応じた選び方が大切です。
ここでは、以下の3つの花について解説していきます。
・枕花
・花環
・献花
供花とは別物であるため、それぞれの違いを理解しておきましょう。
枕花
枕花(まくらばな)とは、亡くなられた方の枕元に静かに手向ける花のことをいいます。病院や自宅でのご安置の際や、通夜の前など、葬儀が始まる前のタイミングで用意されるのが一般的です。
顔のすぐそばに飾られるため、香りが強すぎない花が選ばれます。たとえば、白いユリ、カーネーション、菊など、控えめで清らかな印象の花がよく使われています。
枕花は通常、ご遺族やごく親しい親族が準備するものであり、一般の参列者や知人が贈ることはあまりありません。サイズも大きすぎないものが好まれ、花瓶に生けるタイプや、コンパクトなアレンジメントでまとめられることが多いです。
花環
花環(はなわ)は、大きな円形に花を飾り付けた装飾で、主に屋外に設置される供花の一種です。かつては葬儀場の入口にずらりと並ぶ光景が一般的でしたが、近年はその姿も地域によってさまざまに変化しています。
たとえば、地方では今でも企業や団体から花環が贈られることがありますが、都市部ではスペースの制約や景観への配慮から、取り扱いを控える式場も少なくありません。また、式の雰囲気によっては、花環が場にそぐわない場合もあるため注意が必要です。
花環は非常に目立つため、贈る際には自己判断で手配するのではなく、必ず遺族や葬儀社に事前確認を取りましょう。
献花
献花(けんか)とは、葬儀の参列者が直接祭壇に供える小さな花のことを指します。もともとはキリスト教の葬儀でよく行われていた形式ですが、近年では仏式や無宗教の葬儀でも取り入れられる機会が増えています。
そのため、宗派に関係なく幅広い場面で目にするようになりました。たとえば、白いカーネーションや菊、ユリといった清楚な印象の花を、祭壇の前に静かに手向けることで、故人への祈りや感謝の気持ちを表現できます。
また、このような花は見た目にも落ち着きがあり、葬儀の厳かな雰囲気にもよくなじみます。さらに、宗教の形式によっては焼香の代わりに献花を行う場合もあるため、あらかじめ葬儀の流れや作法を確認しておくことが大切です。
供花の手配方法
供花を手配する際には、自分の立場や故人との関係性に合わせて、ふさわしい方法を選ぶことが大切です。主な手配手段として、以下の4つがあります。
・葬儀社に依頼する
・花屋に依頼する
・インターネットで手配する
・遺族を通して依頼する
それぞれにメリットや注意点があるため、状況に応じて最適な方法を選びましょう。ここでは、それぞれの手配方法の特徴や流れについて詳しく解説します。
葬儀社に依頼する
もっとも確実で安心な方法は、葬儀を担当する葬儀社に供花の手配を依頼することです。葬儀社は会場の構成や遺族の希望を把握しているため、会場の広さや祭壇とのバランスを踏まえて、適切なサイズや形式、本数などを提案してくれます。
たとえば、喪主が「白を基調にした落ち着いた雰囲気でまとめたい」と希望している場合には、白菊や白ユリを中心としたスタンド花を提案し、ほかの供花とデザインが調和するよう配慮してくれるでしょう。
さらに、宗派や地域特有の風習にも精通しているため「この地域では菊よりもカーネーションを使うことが多い」といった事情にも柔軟に対応してもらえます。供花のマナーに不安がある方や、急な訃報で準備に時間をかけられない方にとっては葬儀社に一任することで、失礼のない対応ができ、安心して手続きを進められます。
花屋に依頼する
地域の花屋に直接依頼するという方法も、有力な選択肢のひとつです。地元に根ざした花屋であれば、その土地ならではの風習や宗教ごとのマナーにも詳しく、細やかな対応が期待できます。
たとえば「仏式の葬儀なので、白菊をメインに落ち着いた色味でまとめてほしい」と伝えれば、白菊に加えて白ユリやカスミソウを組み合わせた上品なアレンジメントを提案してくれるでしょう。
ただし、葬儀式場への納品手配や配置の調整などは、基本的に依頼者自身が行う必要があります。とくに、式場によっては搬入時間が厳しく決まっていたり、指定の搬入口を利用するよう求められることもあるため、事前に式場とのやり取りをしっかり済ませておくことが重要です。
時間や段取りに余裕があり、信頼できる地元の花屋がある方には、おすすめの方法といえるでしょう。
インターネットで手配する
最近では、インターネット専門の花屋やECサイトを利用して、供花を手配する人が増えています。ネット注文の最大の魅力は、時間を問わず24時間いつでも申し込める点にあります。
仕事や家庭の都合で日中に動けない方でも、夜間にゆっくり選べるのは大きなメリットといえるでしょう。また、実店舗よりも価格帯が抑えられていることが多く、同じ予算でもボリュームやデザイン性の高い供花を選べるのも魅力です。
注文の流れはシンプルで、希望する供花を選び、葬儀の日時や会場、故人の名前、送り主の情報を入力し、決済を済ませるだけとなっています。ただし、注文の際には葬儀の詳細(日時・場所・宗教形式など)を正確に把握しておく必要があります。
配送地域に制限があるケースもあるため、会場が対応エリア内かどうかを事前に確認することも忘れずに行いましょう。
遺族を通して依頼する
供花の手配を遺族に直接お願いする方法もあります。とくに家族葬では供花を統一していることが多く「個別の注文はご遠慮ください」と案内されることもあります。
どうしても贈りたい場合は、まず遺族に確認し「供花代としてお包みしてもよろしいでしょうか」と申し出たうえで、指示に従い振込や香典と一緒に渡すのが一般的です。この方法なら遺族への配慮を忘れず、気持ちもきちんと伝えられます。
供花を贈る際のマナー
供花を贈る際には、宗教や地域の風習、そして遺族の意向に配慮したうえで、適切なマナーを守ることが大切です。形式を誤ると遺族に負担をかけてしまう場合があるため、以下のポイントを押さえておきましょう。
・遺族や葬儀社に事前に確認する
・故人との関係性を明確にする
・通夜の前に届くよう手配する
・祭壇に合わせた色味を選ぶ
・札名は正確に記載する
これらのマナーを丁寧に守ることで、気持ちがきちんと伝わり、遺族にも安心して受け取ってもらえます。ここでは、供花を贈る際に気をつけるべきマナーについて詳しく解説します。
遺族や葬儀社に確認する
供花を手配する際には、まず遺族や葬儀社へ確認を取ることが最も基本的なマナーです。近年では、家族葬などの小規模な葬儀が主流となりつつあり、会場に飾れる供花の数が限られていることも珍しくありません。
また、あらかじめ「供花はご遠慮ください」と告知されるケースも増えています。こうした事情を無視して供花を送ってしまうと、思いやりのつもりがかえって遺族の負担となってしまう可能性があります。
確認の方法としては、遺族に「供花をお贈りしたいのですが、よろしいでしょうか」と丁寧に声をかけるのが一般的です。直接聞きにくい場合は、葬儀を担当している葬儀社に連絡し「供花の受付はされていますか?」と確認してみましょう。
とくに家族葬では、遺族の意向を最優先にすることが大切です。万が一、供花を辞退されていた場合には、無理に贈ろうとせず、後日お悔やみの言葉を伝えるなど、別の形で想いを届ける方法を検討するとよいでしょう。
故人との関係性を明確にする
供花を贈る際には、故人との関係性を明確にしておくことが大切です。関係性によって贈るタイミングや花の形式、札名の記載方法が異なるためです。
たとえば、親族であれば一対のスタンド花を贈るのが一般的であり、会社関係であれば社名と役職を札に記載します。葬儀にふさわしい礼儀を守るためにも、贈る立場に応じた供花を選ぶ意識が必要です。
通夜の前に届くように手配する
供花を贈る際は、通夜の前までに到着するように手配するのが基本的なマナーです。通夜や葬儀の直前は遺族や葬儀社にとって非常に慌ただしい時間帯となるため、供花の受け取りや設置の対応が難しくなってしまいます。
とくに会場の設営が始まるタイミングと重なると、供花の配置場所が確保できなかったり、式の進行に支障が出たりすることもあります。たとえば、通夜が午後6時から予定されている場合は、当日の午前中、遅くとも正午までには到着するように手配しておくと安心です。
また、インターネット注文や花屋を通じて手配する際には、葬儀会場の名称、住所、式の開始時間、そして「通夜用の供花である」旨を正確に伝えておくことが重要です。これにより、現地のスタッフがスムーズに対応でき、見栄えよく設置してもらえる確率が高まります。
通夜や葬儀の時間を逆算し、できるだけ余裕をもったスケジュールで準備することが、失礼のない弔意の表し方といえるでしょう。
色味は祭壇に合わせる
供花として選ぶ花の色は、祭壇全体の雰囲気や葬儀の形式に合わせて慎重に決めることが大切です。とくに仏式の葬儀では、白を基調とした清楚で落ち着いた色合いが基本とされており、淡い紫や薄いピンクなど控えめなトーンの花が好まれます。
具体的には、白菊や白ユリ、トルコキキョウといった花が定番で、厳かな雰囲気の中でも自然に調和するため多くの場面で用いられています。一方で、赤や黄色、濃いピンクなど鮮やかな色合いの花は、式の雰囲気に合わず場違いな印象を与えてしまうこともあるため、注意が必要です。
さらに、宗教や地域によって花に対するとらえ方が異なることもあるため、故人の宗派やご遺族の意向にしっかりと配慮したうえで花を選ぶようにしましょう。
札名は正確に記載する
供花に添える札名(立て札)には、送り主の名前を正確に記載することが重要です。札名は、供花を贈った相手が誰であるかを明確にする役割を果たし、遺族が後日お礼状を送る際の大切な手がかりにもなります。
個人で贈る場合は「姓名」夫婦であれば「姓 夫妻」法人名義であれば「社名と代表者名」と記載するのが一般的な形式です。
供花に添える札名の書き方
供花に添える札名(ふだな)は、故人への弔意を表し、誰が供花を贈ったのかを明確にするために重要なものです。しかし、札名の書き方には一定のルールがあり、失礼のないように注意する必要があります。
送り主の立場や故人との関係性によって、札名の書き方にはいくつかのパターンがあります。
・親族として贈る場合
・夫婦で贈る場合
・友人として贈る場合
・会社として贈る場合
・複数人で連名で贈る場合
・外国の方が贈る場合
それぞれの立場に応じた適切な札名の書き方を知ることで、失礼のない形で供花を贈れます。ここからは、各ケース別の札名の書き方について詳しく解説します。
親族で贈りたい場合
親族全体で供花を贈る際は「親族一同」や「山田家親戚一同」とまとめて記載します。これにより、多数の親族からの弔意をひとつにまとめて伝えられます。
たとえば、故人の兄弟姉妹やその家族全員で供花を贈る場合「兄弟姉妹一同」や「親族一同」と記載します。親族の場合は、亡くなった方との血縁関係や姻戚関係がはっきりと分かるように記載することで、弔問客や遺族が供花を贈った方と故人の関係性を理解しやすくなります。
なお、親族として供花を贈る場合は、事前に喪主やほかの親族と相談し、重複を避けることも大切です。
夫婦で贈りたい場合
夫婦で供花を贈る際の札名には、いくつかの記載方法があります。伝統的には、夫の氏名のみを記載するのが一般的とされており、とくに格式を重んじる場面ではこの形式が好まれます。
ただし、最近では夫婦連名での記載も受け入れられるようになってきており、より柔軟な対応が見られるようになりました。その場合は、縦書きで右から左へと記載し、右側に夫のフルネーム、左側に妻の名前のみを添えるのが基本です。
たとえば「山田太郎 花子」という形式がよく用いられます。なお、苗字を繰り返して「山田太郎 山田花子」と書くのは避けましょう。さらに、子どもの名前を加える場合は「山田太郎 花子 一郎」のように、夫、妻、子どもの順で右から並べるのが適切です。
友人で贈りたい場合
友人として供花を贈る際には、送り主が誰であるかをはっきり伝えるために、フルネームで記載するのが基本です。たとえば「佐藤一郎」のように、個人としての名前を丁寧に書きましょう。
また、学生時代の友人や旧友など、複数人で連名にする場合は「○○高校 同級生一同」「大学時代の友人一同」などと関係性を加えると、遺族にも分かりやすくなります。単に名前を並べるよりも、どのようなつながりがあったかを添えることで、故人との関係性をより丁寧に伝えられます。
会社で贈りたい場合
会社から供花を贈る際は、企業としての立場を伝えるために、会社名に加えて部署名や役職を明記するのが一般的です。たとえば「株式会社ABC 営業部一同」や「株式会社ABC 代表取締役 田中一郎」といった記載がよく用いられます。
こうした表記により、個人ではなく組織として弔意を表していることが明確になり、遺族への配慮や敬意を伝えられます。
連名で贈りたい場合
友人や同僚など複数人で供花を贈る際には、連名で札名を記載するのが一般的です。名前はフルネームで縦書きになるため、2~4名までが目安となります。
それ以上の人数になる場合は「田中一郎 外〇名」や「同期一同」「有志一同」などと、まとめた表記にすると見た目もすっきりし、形式としても適切です。また、連名で記載する際には順番にも配慮が必要です。
縦書きの札名では、右側から順に名前が並ぶため、肩書きや役職に違いがある場合は、地位の高い人を一番右に配置します。肩書きに明確な差がない場合は、五十音順で並べると整った印象になり、誰にとっても公平な書き方といえるでしょう。
外国の方が贈りたい場合
外国の方が供花を贈る場合は、アルファベットではなく、カタカナのみで名前を記載するのが望ましいとされています。たとえば「ジョン・スミス」のように表記することで、読みやすくなり、遺族への配慮にもつながります。
供花に関するQ&A
葬儀の供花に関して、多くの方が抱きやすい以下の疑問について解説します。
・供花の適切な金額はいくらか
・供花と香典は両方必要か
残った疑問を解消して故人や遺族に対して失礼のないよう、マナーを守りながら心のこもった弔意を表しましょう。
供花の相場はいくら?
供花の費用は、贈る形や地域の習慣によって多少異なりますが、一般的には1基あたりおよそ7,500円〜30,000円程度が目安とされています。一対(2基)で贈る場合は、15,000円〜30,000円前後が相場です。
さらに、供花の注文には札名の作成料や配送料が別途かかることもあるため、依頼する際には総額の見積もりを事前に確認しておくと安心です。
供花と香典は両方渡すべき?
供花と香典は、必ずしも両方用意しなければならないものではありません。どちらか一方だけでも失礼にはあたりませんが、故人との関係が深かった場合や、親族として参列する場合などには、供花と香典の両方を用意することが一般的です。
たとえば、長年お世話になった上司や親しい親戚の葬儀であれば「供花+香典」で弔意を表す方が丁寧な印象になります。一方、遠方に住んでいて葬儀に参列できない場合などは、供花のみを手配する、または香典だけを郵送するという対応でも問題ありません。
こちらの記事では、香典について解説しています。 香典の金額や不祝儀袋の注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
本記事では、供花を贈る際に知っておきたい基本的なマナーや、手配までの流れについて詳しくご紹介しました。供花は、故人への哀悼の気持ちや、遺族への思いやりを形にする大切な方法のひとつです。
そのため、宗教や地域ごとの慣習に合わせた花の選び方、札名の正しい書き方、手配のタイミングなど、事前に把握しておくべきポイントが数多く存在します。こうした細やかな配慮を重ねることが、結果として遺族に対する丁寧な姿勢や、失礼のない弔意の表現につながるでしょう。
とはいえ「どのように準備を進めればよいのかわからない」「宗教ごとの違いに自信がない」と不安を抱く方も少なくありません。そんなときは、メモリードのお葬式へご相談ください。
全国に210か所の葬祭関連施設を展開し、年間約2万件以上の葬儀を支えてきた実績を持つメモリードグループには、217名の一級葬祭ディレクターが在籍しています。供花の手配だけでなく、終活に関するご相談や葬儀後のアフターサポートにいたるまで、幅広く対応しております。
故人との最後のお別れを、丁寧で誠実な形で迎えたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。