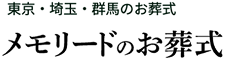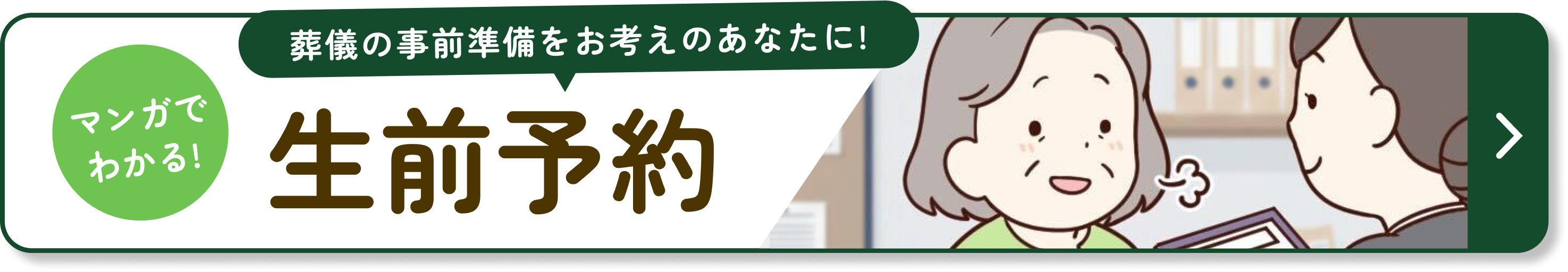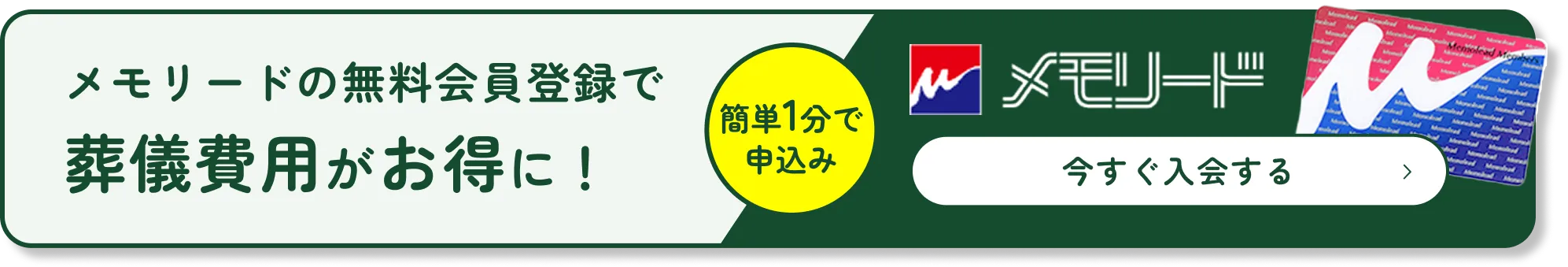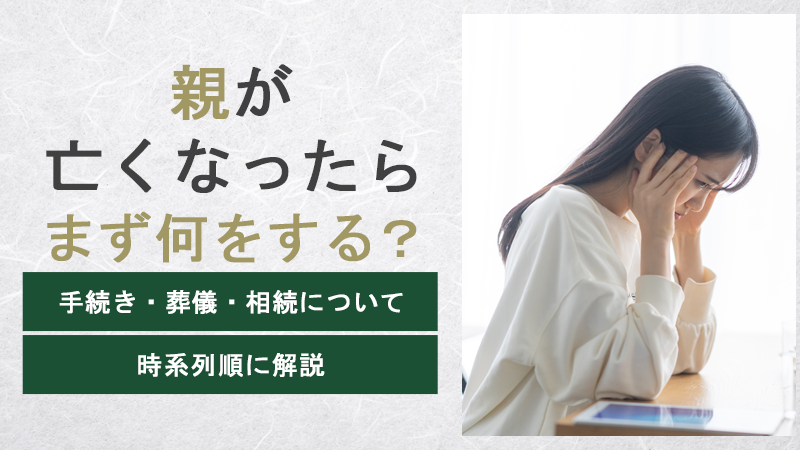親しいご家族を見送ることは、深い悲しみのなかにあっても、さまざまな対応を求められる大変な時期です。お葬式の準備や行政・銀行・保険などの手続き、相続に関することなど、限られた時間のなかで進めていかなければならないことが多くあります。
なかには期限が決まっている手続きもあるため、思いがけず慌ただしく感じてしまう方もいるかもしれません。
本記事では、親が亡くなった後に必要となることを、時系列に沿ってわかりやすくご紹介しています。あらかじめ流れを把握しておくことで気持ちにゆとりが生まれ、故人との大切な時間を落ち着いて過ごせます。ぜひ、参考にしてください。
【当日】親が亡くなったら行うこと・手続き
親が亡くなったその日には、すぐに行わなければならないことがいくつかあります。深い悲しみのなかで冷静に対応するのは難しいことですが、あらかじめやるべきことの流れを知っておくと、少し落ち着いて行動できます。ここでは、親が亡くなった当日に必要になる手続きや対応をご紹介します。
死亡診断書の受け取り
ご家族が亡くなられた際には、まず医師による「死亡確認」が必要となります。病院で亡くなった場合は、担当の医師がその場で「死亡診断書」を作成してくれます。
自宅や介護施設など、病院以外の場所で亡くなった場合は、かかりつけの医師などに来てもらい、診断書の作成を依頼します。もし事故や突然の逝去などにより、医師による診断が難しい場合は、警察を通じて「死体検案書」を作成してもらう必要があります。
いずれの書類も、その後のさまざまな手続きに必要となるため、あらかじめコピーを数部用意しておくと安心です。なお、費用の目安としては、死亡診断書で5,000円〜10,000円ほど、死体検案書は30,000円〜100,000円程度が一般的です。
近親者への連絡
次に、親族や親しい方に電話で連絡をします。最新の連絡先が分からない場合は、ほかの親族に聞いてみましょう。
この時点では、通夜や葬儀の日程が未定でも構いません。「亡くなったこと」と「詳細は後ほどお知らせする」ことを簡潔に伝えます。
葬儀社の選定と打ち合わせ
葬儀社には、できるだけ早めに連絡を入れ、今後の流れについて相談することが大切です。生前のうちにいくつかの葬儀社の資料を取り寄せて比較しておくと、費用や内容の違いが把握しやすく、心構えにもつながります。
打ち合わせでは、葬儀の形式(一般葬・家族葬など)や、通夜・告別式の進め方、ご遺体の搬送・安置場所の決定、火葬場の予約などについて具体的に話し合います。故人のご希望や参列予定の人数、費用の目安なども共有しておくと、その後の準備がよりスムーズになります。
遺体の搬送と安置先の決定
病院の霊安室には長時間安置できないため、ご逝去後は数時間以内にご遺体の搬送先を決める必要があります。搬送先としては、自宅のほか、葬儀社や斎場の安置施設などが選ばれることが一般的です。
ご自宅に安置される場合には、ご遺体を搬入する経路や室内のスペースを事前に確認しておくと、より安心です。
ご遺体の搬送は、通常、葬儀社が専用の車両で丁寧に対応してくれます。深夜や早朝でも対応可能な葬儀社をあらかじめ把握しておくと、いざというときにも心強いでしょう。
葬儀社をまだ決めていない場合でも、まずは搬送のみを依頼し、その後ゆっくりと葬儀の内容や形式について相談を進めることも可能です。焦らず一つひとつ進めていくことが大切です。
【7日目まで】親が亡くなったら行うこと・手続き
親が亡くなった翌日からは、通夜や葬儀の準備とともに、いくつかの手続きも始まります。なかには期限が決まっているものもあるため、流れを知っておくと安心です。
ここからは、亡くなってから7日目までにやるべきことや葬儀の流れをご紹介します。
死亡届の提出
死亡診断書を受け取ったら、7日以内に役所へ死亡届を出します。提出先は「故人の本籍地」「死亡した場所(単身赴任先など)」「届け出をする人の住所地」のいずれかの市区町村役場です。
死亡届と死亡診断書はひとつの用紙になっており、提出の際は原本が必要です。ほかの手続きで必要となるため、あらかじめコピーを取っておきましょう。通常は喪主が提出しますが、葬儀社が代行してくれることもあります。
火葬許可証の取得
死亡届を提出すると、火葬に必要な「火葬許可証」を申請できます。自治体によっては、死亡届を出すと自動的に交付される場合もあります。申請の際には、故人の本籍地や現住所、火葬場名などの情報が必要になるため、あらかじめ控えておくと安心です。
健康保険証の返却
故人が職場の健康保険に入っていた場合は、会社を通じて保険証を返却します。家族が扶養に入っていた場合も手続きが必要なため、早めに会社へ連絡をしましょう。
通夜
通夜は葬儀の前日に行い、親族や親しい友人が集まって故人と最後の時間を過ごします。一般的には亡くなってから2日目か3日目の夜に行われますが、日程は地域の風習や会場の都合によって変わります。
通夜の準備や手配は葬儀社が担当しますが、喪主は遺影写真の準備や棺・祭壇・供花の選定、返礼品の確認、そして代表挨拶など多くの役割を担います。とはいえ、最近は葬儀社がサポートしてくれる内容も多いため、負担を減らせる部分は任せてしまうのがおすすめです。
葬儀告別式
葬儀や告別式は、故人との最期のお別れをする大切な時間です。形式は宗教や地域の習慣によって異なり、近年は「一日葬」などの新しい形も広がっています。
参列者は、献花や焼香、お別れの言葉などを通じて、故人への想いをそれぞれの形で伝えます。式の準備や進行は葬儀社がサポートしてくれることが多いため、事前に打ち合わせをしておくと安心です。
火葬
告別式が終わったら喪主や親族で火葬場へ向かい、故人を火葬します。所要時間はだいたい1〜2時間で、待機中は控室でお茶をいただきながら、静かに故人を偲びつつお待ちいただく時間となります。
火葬後には、ご親族などで食事をともにする「精進落とし(しょうじんおとし)」の席を設けることが一般的です。これは、故人を偲びながら感謝の気持ちを伝える場として行われます。
初七日法要
本来の初七日法要は、亡くなった日を含めて数えて7日目(6日後)に行うのが習わしです。僧侶にお経をあげてもらい、遺族で焼香をして故人の冥福を祈ります。
近年では、参列者の負担軽減や日程調整の都合から、葬儀当日に初七日法要をあわせて行う「繰り上げ初七日」を選ぶ方も増えています。
こちらのページでも、ご逝去からの大まかな葬儀、ご帰宅までの流れをご紹介しています。 あわせてご覧ください。
【14日目まで】親が亡くなったら行うこと・手続き
葬儀が終わってひと息つきたいところですが、その後も期限内に行う手続きがあるため忘れずに行いましょう。ここでは、親が亡くなってから14日以内に必要な手続きを紹介します。
世帯主変更届の提出
親が世帯主だった場合は、亡くなってから14日以内に市区町村の役所に「世帯主変更届」を提出する必要があります。新しい世帯主は、15歳以上のほかの家族から選ばれます。ただし、親が一人暮らしだった場合など、世帯に誰も残っていないときは手続きは不要です。
厚生年金・国民年金の受給停止手続き
親が厚生年金や国民年金を受給していた場合、亡くなった後は年金の支給を停止するための手続きが必要になります。手続きは、日本年金機構や年金相談センターを通じて「受給権者死亡届」を提出します。
この手続きが行われないままだと、年金がそのまま振り込まれてしまい、後日返金のご案内が届くことがあります。遺族にとって思わぬご負担となる場合もあるため、なるべく早めの確認をおすすめします。
なお、故人のマイナンバーが年金機構に登録されている場合には、自動的に停止の手続きが進むこともあります。不明な点がある際は、年金相談窓口に問い合わせて確認しておくと安心です。
国民健康保険の脱退手続き
親が国民健康保険に入っていた場合は、亡くなってから14日以内に保険の資格を失う手続きが必要です。市区町村の役所で保険証や本人確認書類、資格喪失届を提出します。
ただし、自治体によっては死亡届のみの提出で自動で手続きされることもあるため、確認が必要です。親が国民健康保険組合に加入していた場合も、同様に脱退の手続きが必要となります。
介護保険被保険者証の提出
親が介護保険に加入していた場合、介護保険証を市区町村に返却する手続きが必要です。手続きは、亡くなった日から14日以内に市区町村の窓口で行います。
必要な書類は介護保険資格喪失届です。もし介護保険証が見つからない場合は、ケアマネジャーが持っている可能性もあるため、一度確認しましょう。
なお、保険料の未納があれば後日請求書が届くため、案内にしたがって支払います。逆に、払いすぎていた分は返金されることもあります。
後期高齢者医療被保険者資格喪失届の提出
親が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合は、後期高齢者医療被保険者資格喪失届を提出する必要があります。提出期限は亡くなった日から14日以内で、市町村窓口で被保険者証を返還しましょう。
【14日目以降】親が亡くなったら行うこと・手続き
主な行政手続きが一段落しても、その後にも対応が必要なことがいくつかあります。公共料金の解約や保険金の請求、遺産に関する手続きなど、少しずつ整理を進めていくことが大切です。
すべてをすぐに完了させる必要はありませんが、忘れやすい項目もあるため、無理のない範囲で確認しながら進めていきましょう。
公共料金や各種サービスの解約・名義変更
故人が契約していたサービスは、必要に応じて解約や名義変更の手続きを進めていくことになります。そのままにしておくと料金が発生し続ける場合もあるため、状況が落ち着いてから、少しずつ確認を始めていくと安心です。
公共料金
水道・電気・ガスなどの名義変更または解約を行います。手続きは、電気・ガスは各事業者のカスタマーセンター、水道は市区町村の水道局に連絡すれば対応してもらえます。検針票や請求明細があると、手続きがスムーズです。
運転免許証
運転免許証の返納は義務ではありませんが、悪用を防ぐためにも返納がおすすめです。手続きは、最寄りの警察署や運転免許センターで行えます。必要書類は、故人の運転免許証、死亡診断書のコピーや除籍謄本、提出者の本人確認書類などです。
パスポート
パスポートも速やかに返納しましょう。全国のパスポートセンターで対応しています。必要書類は、死亡診断書のコピーや除籍謄本です。形見として残したい場合は、パスポートセンターに相談すれば、無効処理後に返却してもらえます。
その他サービス
スマートフォンやインターネット回線、新聞の購読、クレジットカード、動画配信サービスなど、故人が契約していた可能性のあるサービスは、忘れずに確認が必要です。
契約が見つかった場合は、解約や名義変更の手続きを行いましょう。契約書や利用明細、メールの通知などを手がかりに、あらかじめリストを作っておくと手続きの漏れを防げます。
生命保険の請求と受け取り
親が生命保険に入っていた場合は、保険会社に連絡して保険金の請求手続きをします。請求期限は、死亡日から3年以内です。
主な必要書類は以下のとおりです。
・保険証書 ・除籍謄本(死亡の記載がある戸籍) ・受取人の本人確認書類 ・印鑑
契約によっては、入院給付金や特約による給付金などももらえる場合もあります。保険会社からの案内や契約内容をよく確認し、もれなく請求しましょう。
高額医療費の還付申請
故人が入院や手術などで医療費が高額になっていた場合には「高額療養費制度」を利用することで、一部の費用が払い戻されることがあります。
この制度は、1か月あたりの医療費が一定の自己負担限度額を超えた際に、その超過分が後日支給される仕組みです。申請の窓口は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります:
・会社などの健康保険に加入していた場合:各健康保険組合 ・国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合:お住まいの市区町村役所
申請できるのは、亡くなった日から2年以内です。期限を過ぎると手続きができなくなるため、早めに申請しましょう。
葬祭費・埋葬料の支給申請
葬儀やお墓の準備には多くの費用がかかりますが、公的な制度を利用すれば、一部を補助してもらえることがあります。
・国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合:葬祭費として3〜7万円程度 ・社会保険に加入していた場合:埋葬料として5万円
申請できるのは、実際に葬儀を行った家族などです。申請期限は死亡日から2年以内となっているため、忘れずに手続きを行いましょう。
親が亡くなったときの遺産相続手続き
故人が遺した財産や不動産などをどのように引き継ぐかを決める「相続」の手続きが必要になります。相続は遺族にとって大切な手続きである一方、手順や必要書類が多く、戸惑う方も少なくありません。
あらかじめ相続の流れを知っておくことで、万が一のときにも落ち着いて対応できるようになります。可能であれば、ご家族が元気なうちに希望や考えを共有しておくと、より円滑に手続きを進めることができます。
相続人の調査
まず、遺産を受け取る人(相続人)を確認します。配偶者は必ず相続人となり、そのほかは以下の優先順位となります。
・第1順位:子ども ・第2順位:親(または祖父母) ・第3順位:兄弟姉妹
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、正確に確認しましょう。「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍の内容をひとつの証明書にまとめられるため、銀行や相続税の申告などで何度も戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
遺産の調査
次に、故人が遺した財産の全体像を把握していきます。遺産には、現金・預貯金・不動産・株式などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローンといった「マイナスの財産」も含まれます。
その後の手続きや判断に備えて、できるだけ早い段階で財産を整理しておくことが大切です。万が一、借金などが多く残っていた場合は、ご遺族の負担につながる可能性もあるため、慎重に確認しましょう。
具体的には、銀行口座の残高、不動産の登記簿、固定資産税の通知書、借入金の明細書などを集めて、財産の一覧を作成しておくと安心です。
遺言書の調査と検認
遺言書があると「誰に何を引き継いでほしいか」という故人の気持ちが明確になるため、相続人同士のトラブルを減らすことが可能です。
ただし、故人が手書きで作った遺言書(自筆証書遺言)の場合は、見つけてもすぐに開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という確認の手続きを受ける必要があります。
なお、公証役場で作られた「公正証書遺言」であれば検認は不要です。遺言書は、自宅の引き出しや金庫、公証役場、銀行の貸金庫などに保管されていることが多いため、まずは遺言書があるかどうかを探して確認しましょう。
相続放棄・限定承認
借金が多い場合、そのまま相続すると家族が借金を引き継ぐことになります。そうした場合、相続放棄や限定承認という選択肢があります。
・相続放棄:財産も借金も一切受け取らない ・限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を返す(相続人全員の同意が必要)
どちらの手続きも、相続を知ってから3か月以内に行わなければなりません。早めの判断が大切です。
遺産分割協議
遺言書がない場合や、遺言に詳しい分け方が書かれていないときは、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合わなければなりません。これを「遺産分割協議」といいます。全員の合意が必要で、話し合いの内容は遺産分割協議書という書類にまとめます。
もし話し合いがうまくいかないときは、家庭裁判所に調停や審判をお願いすることも可能です。家族の間でトラブルになりそうなときは、早めに弁護士に相談すると安心です。
亡くなった親の銀行口座はどうなる?
親が亡くなった後、銀行口座はどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。本人が亡くなったことが銀行に伝わると、その口座は凍結されて、お金を引き出せなくなります。
これは、相続人による勝手な引き出しや、遺産トラブルを防ぐためです。葬儀代や生活費など急な出費に備えるためにも、口座凍結の仕組みや必要な手続きをあらかじめ知っておくことが大切です。
凍結前にお金を引き出すことは問題ない
親の口座が凍結される前なら、お金を引き出しても問題ありません。ただし、そのお金は相続人全員の財産にあたるため、使い道を記録しておくとトラブルを防げます。
遺産相続でトラブルになりそうなら凍結がおすすめ
「誰かが勝手にお金を引き出しそう」「財産の分け方で揉めそう」など、相続でトラブルになりそうなときは、早めに金融機関に連絡して口座を凍結してもらいましょう。凍結しておくことで、お金を勝手に使われるのを防げます。
凍結後に口座を引き継ぐには?
凍結された口座からお金を引き出すためには、相続の手続きが終わったことを銀行に証明する必要があります。必要な書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
一般的には、以下のような書類が必要です。
・手続きする人の本人確認書類 ・故人の通帳やキャッシュカード(貸金庫なら鍵も) ・故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのもの)
また、遺言書がある場合は、遺言書や家庭裁判所の検認済み書類、印鑑証明書なども必要になります。遺言がない場合は、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、そして遺産分割協議書も用意しましょう。
親が亡くなった後の税金の手続きと支払い
親が亡くなった後、遺産の整理や相続の手続きに加えて、税金の申告や支払いも必要になります。とくに、相続税や準確定申告など期限が決まっているものも多いため、あらかじめ確認しておきましょう。
所得税の準確定申告
自営業やフリーランスなどで確定申告が必要だった方が亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わりに申告・納税する必要があります。これを準確定申告といいます。
申告の期限は、相続があったことを知った日の翌日から4か月以内です。故人が住んでいた地域を担当する税務署に準確定申告書を提出します。会社員など確定申告が不要な方であれば、この手続きも必要ありません。
固定資産税
故人が不動産を持っていた場合、その固定資産税は相続人が引き継いで支払うことになります。不動産は持っているだけで毎年税金がかかるため、住まない場合は売却や賃貸などを考えましょう。
その年の1月1日時点で誰が所有しているかによって支払う人が決まりますが、所有者がまだ決まっていない場合は相続人全員で支払うことになります。支払期限は延長されないため、遅れると延滞金がかかってしまいます。
相続税
親などから受け継いだ財産の合計が「600万円×法定相続人の人数+3,000万円」の基礎控除額を超えると、相続税がかかります。財産には現金や預貯金、不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含めて合計して判断します。
相続税は基本的に現金で一括払いです。不動産ばかりを相続した場合など、すぐに現金を用意するのが難しいこともあります。その場合は、税務署に相談すると延納や物納といった方法も使えます。
・延納:分割払いが可能 ・物納:お金ではなく土地や建物などを税金の代わりに納める方法
申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。忘れないように早めに準備しておくのが安心です。
メモリードのお葬式では、葬儀に関する相談を受け付けております。 葬儀に関する事前相談などにも対応しています。 お困りの際にはぜひお問い合わせください。
まとめ
親が亡くなった後は、死亡届や火葬許可証の提出、葬儀準備など多くの対応に追われます。喪主は式場や搬送先の手配、参列者への連絡など負担も大きくなりますが、事前に葬儀社へ相談しておくと安心です。
葬儀後も、保険・年金・名義変更などの手続きが続くため、早めの確認が重要です。遺言書やエンディングノートがあれば相続手続きも円滑に進むほか、必要に応じて専門家のサポートを受けることも選択肢のひとつです。
東京・埼玉・群馬を中心に展開するメモリードのお葬式では、葬儀前のご相談から、法要、返礼品、遺品整理、相続の手続きまでをトータルサポートしています。厚生労働省認定の一級葬祭ディレクターが、ご遺族の気持ちに寄り添いながら丁寧にご案内します。
全国に210か所の施設を展開し、年間2万件以上の実績を持つメモリードのお葬式では、ホテルのような控室やバスルーム、料理人常駐の厨房など、快適な空間づくりが特徴です。大切な人との最後の時間を、安心して過ごせるように心をこめてお手伝いします。お気軽にご相談ください。