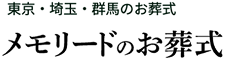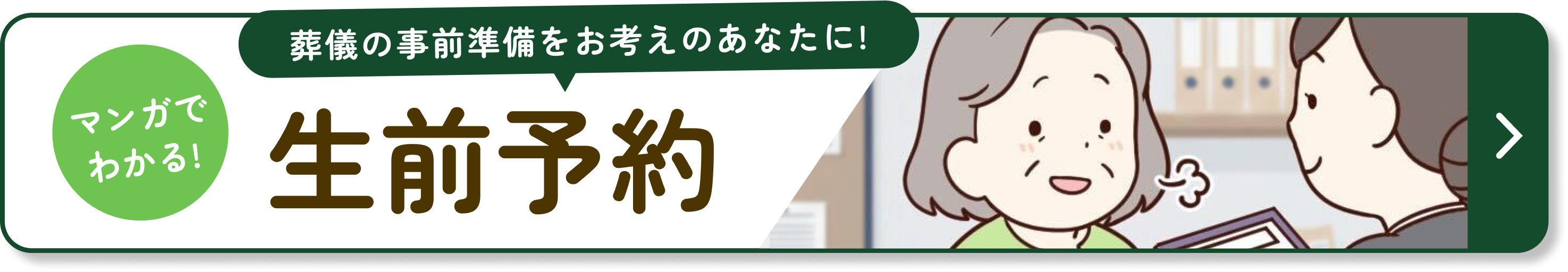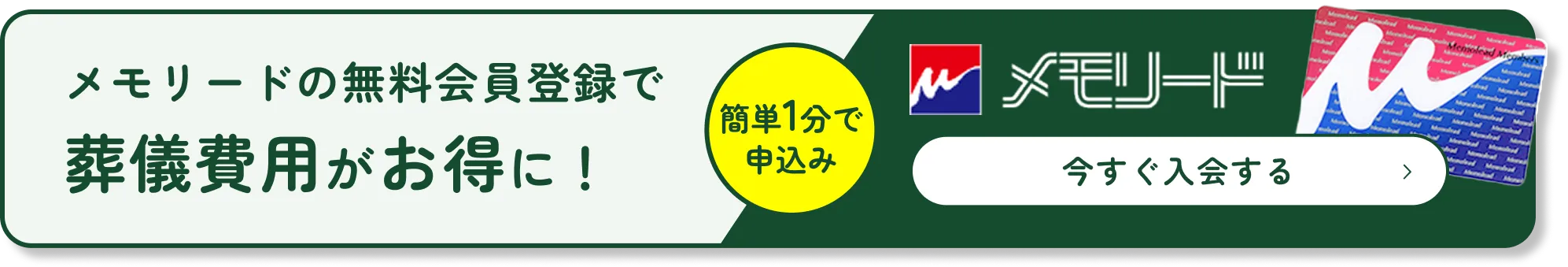キリスト教での「法要」
人が亡くなった後に供養をする意味で用いられる『法要』という言葉は、仏教においてのみ使用されています。それではキリスト教ではなんというのか、ご存知でしょうか?
日本では仏式の法要が一般的です。キリスト教の儀式に出席する機会は少ないかもしれません。
キリスト教式は、仏式とは進行や式次第の違いが多くありますので、初めて参列する場合はわからない事が多いでしょう。
キリスト教式の儀式に参列する際、ついつい仏教用語を使ってしまったり、どのように動けば良いのか分からずに戸惑ってしまうこともするかもしれません。
少しでもキリスト教式の儀式について知っておけば、いざという時に役立つと思います。
また同じキリスト教でも
「カトリック」
「プロテスタント」
と教派があります。
それによって法要の行われ方も変わってきますので、区別してお話していきます。
カトリックについて
カトリックでは、法事・法要に当たる儀式のことを「追悼ミサ(追悼式)」と呼びます。人が亡くなり肉体が滅んでも、霊魂は神の御許(みもと)に召されて、永遠の生命が始まると考えられています。
人が亡くなってから3日目、7日目、30日目という節目の時期に、教会で追悼ミサが行われます。
そして、昇天日といわれている命日にあたる1年目にも追悼ミサを行います。
仏式の法要は、故人の冥福を願う供養のものですが、もともとキリスト教にはそういった概念がありません。
キリスト教では供養というよりも、故人を思い出して皆で懐かしみ、思い出話をするような感覚で行なわれます。
仏式では、忌日法要や年忌法要のように、法要を行う日が決まっています。しかしキリスト教では、亡くなってから追悼ミサをいつ行うかという時期についてきちんとした決まりはありません。
ですが、大まかには、3年目、5年目、7年目というのが主流となっています。
追悼ミサでは、進行を【神父*】が行い、参列者がみんなで聖歌を歌い、聖書の朗読や祈りを捧げます。
その後に、軽く茶話会を開き、故人を偲びます。
また、カトリックでは亡くなった方すべての追悼の意味を込めて、
毎年11月2日を万霊節(オールソウルズデイ)とし、 この日に追悼ミサを行います。
万霊節には、教会でミサをした後、お墓に行き、お花をそえます。
プロテスタントについて
プロテスタント式では法事・法要に当たる儀式のことを、「記念集会」と言います。
こちらもカトリック同様、正式な細かい決まりはないのですが、 亡くなってから1週間後、1か月後に教会や自宅などで、行なわれます。
特に1か月後の「昇天記念日」と呼ばれる日には、家族や親族、友人の集まりを行うことが多くなっています。
プロテスタントでは【牧師*】が式を信仰していきます。
祈りをささげ、聖書を朗読し、全員で讃美歌を歌うという流れで進めていきます。
礼拝が終わったら、茶話会で参列者をもてなし、故人を偲ぶ会となります。
1年目の命日を過ぎたら、3年目や7年目といった区切りで行うことが多いです。
しかしこれも、細かい取り決めはありません。
このようにキリスト教は、仏式の法要のような細かな決まりはなく、家族の気持ちでそれぞれ行われ方も異なってきます。
仏式とキリスト教式では、このように考え方や時期も異なることを理解しておくと良いでしょう。
*「神父」はカトリックの聖職者に対する尊称で、「牧師」はプロテスタントの教職者の職名です。