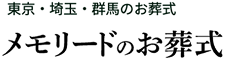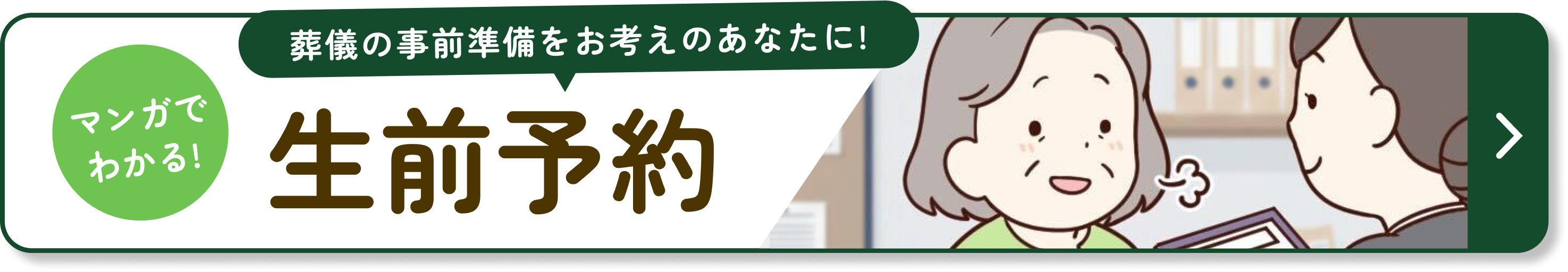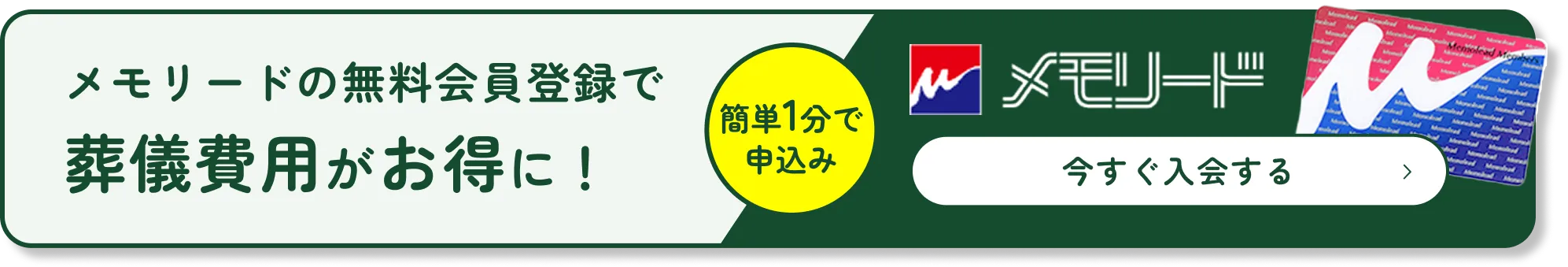お盆とは?
日本に古くから伝わる、伝統的な行事のひとつ、お盆。
先祖を祀る夏の行事で、先祖の霊がこの世に戻ってくると言い伝えられています
それでは、お盆の意味や迎え方について、紹介していきましょう。
全国的にみて、"お盆 = 夏"というのは変わりませんが、地域によって時期が異なります。
7月13日からの「新盆」と8月13日からの「旧盆」の二種類がございます。大多数の地域では"お盆 = 8月"となっていますが、例えば東京の一部の地域では7月にお盆を迎えるところもあります。
お盆の準備
お盆は亡くなった先祖が帰ってきますので、様々な準備が必要です。
盆棚
まず、仏壇を綺麗にすることはもちろんなのですが、一般的に「盆棚」と言われる
特別な飾り付けも施します。
季節の野菜や果物、精進料理、お菓子、お花などを添えます。
特にきゅうり、なすを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
きゅうりは馬を表し、早くこの世に戻って来れるようにという意味が、
なすは牛を表し、お盆の終わりにゆっくりとした足取りであの世に戻れるようにという意味が込められています。
迎え火・送り火
お盆が始まる13日の夕方には、この世に帰ってくる先祖が道に迷わないように「迎え火」をあげる風習があります。
仏壇に盆提灯を飾ったり、玄関先でおがら(皮を剥ぎとった麻の茎)を炊いたりします。
また、お盆が終わる16日には先祖をあの世へ送り出すための「送り火"」があります。
地域や宗派によって内容が異なる
盆棚に飾るものや、その他諸々のしきたりは地域や宗派によって違いが出てきます。
そもそも浄土真宗では前述の準備をほとんど行いません。
なぜなら、お盆に先祖が帰ってくるという考え方がないのです。
ですので特別な準備は行いませんが、供養はしっかりと行う時期になります。
新盆
7月や8月のお盆に関わらず、「新盆(初盆)」には故人が亡くなってから最初に迎えるお盆という意味合いもあります。
最初のお盆は通常のお盆に比べいくらか盛大に行います。
身内や親族も読んで僧侶に読経していただいたり、集まってくれた方たちへ
会食でもてなしたりするケースが多くあります。
新盆(初盆)
忌明け後に最初に迎えるお盆のことを"新盆"あるいは"初盆"と言います。亡くなった方の例が初めて戻ってくるというタイミングになりますので、特に重要とされています。
仏壇の前に精霊棚を設けて、故人の好物などを供えます。また、故人の霊が迷わないようにするために、提灯を飾り分かりやすくしてあげます。身内や親しい人たちでお墓参りをして、精霊棚だけではなく墓前にも故人の好物や花、線香などを供えます。
お寺様に関しては、一般的には自宅に招きますが、お墓参りに同行してもらうという場合もあります。なお、忌明け法要よりも前にお盆を迎えた場合には勝手が違いまして、その年の新盆(初盆)は行いません。