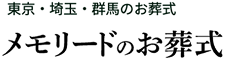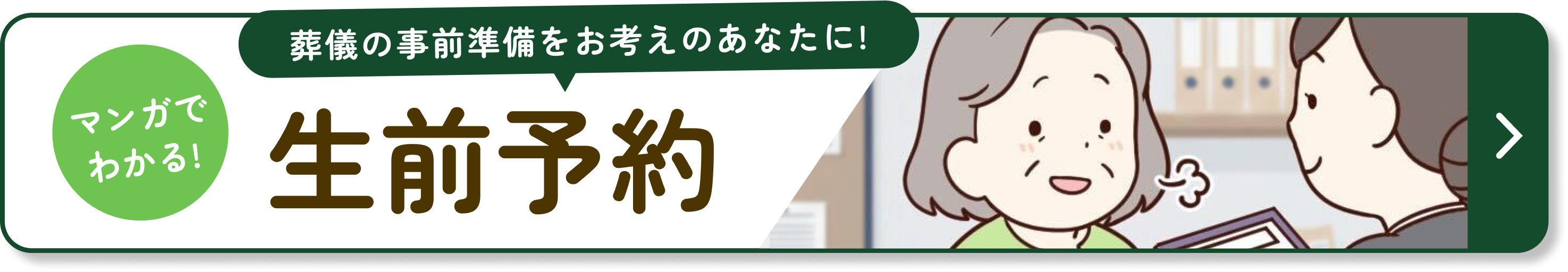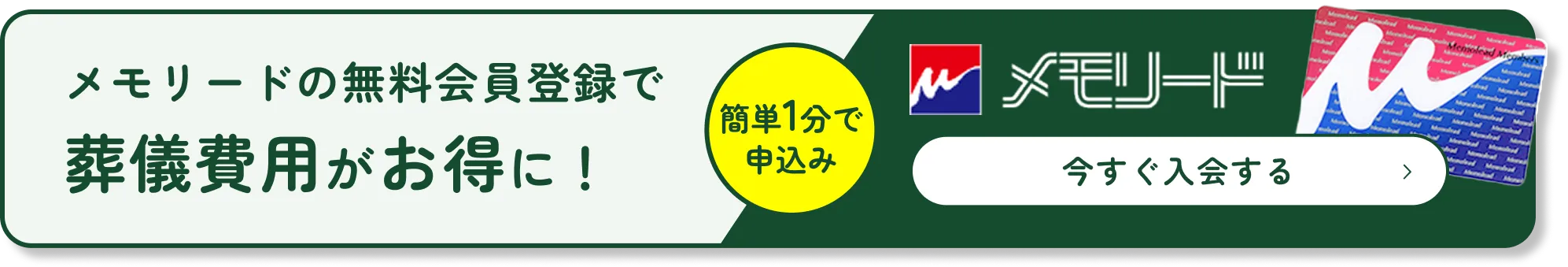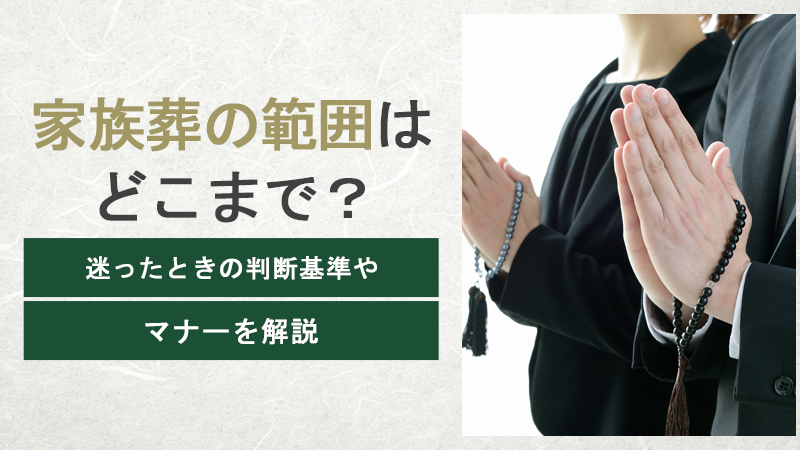「家族葬ってどこまで呼べばいいの?」と悩んでいませんか?近年、家族やごく親しい人だけで故人を見送る「家族葬」を選ぶ人が増えています。
いざ自分が喪主や遺族となったときに「家族葬ではどこまでの人を呼べばいいのか」「親族以外に参列してもらってもよいのか」と迷うこともあるのではないでしょうか。正解がないともいわれる家族葬ですが、事例やマナーを知っておくことで、後悔のない選択がしやすくなります。
本記事では、家族葬における招待の範囲や招く人の判断ポイントから、参列者としてのマナーについてまで、具体例を交えながらわかりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。
家族葬はどこまでの範囲を指す?
「家族葬はどこまでの人を呼ぶべきか」と考えるとき、2つの立場からの視点が存在します。ひとつは喪主や遺族側の立場、もうひとつは参列を希望する側の立場です。しかし、どこまで招くべきかという問いに対しての明確な答えはありません。
「誰を家族葬に招待するか」または「自分は家族葬に参列してもいいのか」という2つの視点で考えてみましょう。家族葬に明確な定義はありませんが、公正取引委員会は目安として以下のように定めています。
・親族や親しいご友人など親しい関係者のみで行う葬儀
・参列者数が50名未満の小規模な葬儀
このように、家族葬は、故人と親密な関係にあった人たちだけで営まれる葬儀です。招待される参列者の人数は10〜50名程度が多く、基本的には故人の配偶者・子・兄弟姉妹・孫など二親等以内の親族が中心となるでしょう。
一方で、故人が生前とくに親しくしていた友人や、職場関係で深いつながりのあった人を招くケースもあります。反対に、形式的な参列や香典を避けたいという遺族の意向から、親族の一部や知人でも招かれないケースも考えられるでしょう。
こちらの記事では、家族葬について解説しています。 家族葬の流れや注意点も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
【遺族】家族葬に招く人を決める基準
家族葬を行うにあたって「どこまでの人を呼ぶべきか」と頭を悩ませる遺族は少なくありません。親族間で意見が食い違うことも多く、招待の範囲は、後々の人間関係にも影響します。ここでは、判断の参考となる基準を5つご紹介します。
二親等以内の親族
家族葬の基本は、故人と深い関係にあった人だけで執り行うことです。まず考慮されるのが、二親等以内の親族です。具体的には、配偶者・子・孫・親・兄弟姉妹などが該当し、日常的な交流がある場合が多く、家族葬における基本的な招待範囲といえるでしょう。
故人ととくに親しかった人
血のつながりがなくても、故人ととくに親しくしていた人を招くこともあります。たとえば、古くからの友人や、職場の上司や同僚などが該当します。
故人が生前に「この人には最期を見送ってもらいたい」と話していた相手がいる場合には、その意志を尊重して招待するとよいでしょう。
今後の関係性をこじらせたくない人
家族葬では、招待されなかったことによるわだかまりによって、葬儀後に気まずい関係になるケースも考えられます。とくに、親戚として付き合いが続く人に対しては、円滑な関係を維持するために招待することもひとつの選択肢です。
基本的には、故人との関係性を最優先に考えるべきですが、自分だけ呼ばれなかったという思いを残させないための配慮も、今後の円満な関係を築くうえでは大切なことです。遺族としての意向も取り入れながら招く人を決めましょう。
迷ったら呼ぶのが無難
招待するか迷うということは、それだけ故人や遺族にとって大切な存在だったといえます。とくに、故人を慕っていた親族などは、呼ばれなかったことで心を痛める可能性もあります。
故人や遺族にとって大切な存在だからこそ、迷ったときは招待するのが無難といえるでしょう。
招く基準をはっきりさせることも重要
誰を招くかの基準があいまいなまま参列者を決定すると「あの人は呼んだのに、なぜこの人は呼ばなかったのか」と指摘を受ける可能性があります。
そうしたトラブルを防ぐためにも、血縁の近さ、故人との関係性、今後の付き合いなどの判断基準を家族内で統一しておくとよいでしょう。
【遺族】家族葬の招待範囲の事例
家族葬の招待範囲に明確なルールはなく、遺族の判断によって大きく異なります。しかし、実際の事例を知ることで、自分たちがどこまで招くべきかの参考となります。ここでは、規模の異なる4つのケースをご紹介します。
ケース1:10人程度・身近な親族のみ
最も小規模な家族葬では配偶者や子ども、両親など、ごく近しい親族のみが参列する形式です。故人が高齢で周囲との交流が少なかった場合や、家族のみで静かな見送りを望むときに選ばれます。会場も自宅や小規模な会館で執り行うことが多く、費用を抑えられる点も特徴といえます。
ケース2:20人程度・故人の兄弟やいとこなども
少し広い範囲として、兄弟姉妹やいとこなども含めた親族を招くケースです。
「普段から関わりのある親戚までは招こう」と考える遺族も多いことから、親戚付き合いの頻度によって招待範囲が判断されるパターンです。この規模になると斎場を利用することが多く、やや一般葬に近い印象を与えます。
ケース3:30人程度・故人の義家族や甥姪なども
さらに、広い招待範囲となるのが、義理の家族や甥姪など故人とのつながりが深かった人々を招く家族葬です。家族同士の交流が密だった場合や、義家族とも強い絆があったときに検討されることが多いでしょう。
人数が増えると「家族葬の範囲を超えているのでは」と心配になる方もいるかもしれませんが、あくまで「告知をせず、故人と深くつながりのある人だけで営む」ことが家族葬です。人数に左右されず、故人との関係性を軸に考えましょう。
ケース4:50人程度・故人の同僚や友人なども
家族葬であっても、故人の生前の交友関係を大切にしたいという思いから、友人や職場の関係者を招くケースもあります。このような場合、形式は家族葬であっても、実質的には小規模な一般葬に近い印象を与えることもあるでしょう。
参列者が多くなると、意見の食い違いや誤解が生じやすくなります。招待前に家族内でしっかりと話し合い、意見をすり合わせておくことが重要です。
【遺族】家族葬に招く人への連絡方法
家族葬では参列者が限定されるため、誰にどのタイミングで連絡するかが非常に重要です。連絡の仕方や伝え方次第で、遺族の意図が正しく伝わらないこともあるため、慎重な対応が求められます。
ここでは、家族葬に招く人への連絡方法について、タイミングや手段、注意点を解説します。
身近な親族には危篤の時点で連絡
親や配偶者、子ども、兄弟姉妹などのごく近しい親族には、故人が危篤の段階で連絡を入れるのが一般的です。逝去前の連絡は、最期の時間を故人とともに過ごしてもらうことが目的です。連絡する際は、病院に来られるかを確認するようにしましょう。
ほかの人には逝去後に連絡
いとこや甥姪、義理の家族など、危篤時に連絡するほど近しい間柄ではないものの、葬儀への参列をお願いしたい人には、故人が逝去後に連絡します。
その際、家族葬で執り行うこと、限られた人のみで行うことを一言添えるようにしましょう。人数を絞っている意図を伝えられ、葬儀が行われることが必要以上に広まることを防げます。
手段はメールや電話
連絡手段は電話が基本ですが、急ぎでなければメールでも構いません。近年ではLINEなどのメッセージアプリを使う方も増えています。ハガキは到着までに日数がかかるため、避けた方が安心です。
大切なのは、丁寧で誤解のない文面であることです。「日時、場所、服装、香典の有無」など必要事項を簡潔に伝えると、相手も安心して準備できます。香典や供物、供花を辞退する場合には、参列を依頼する際に合わせて伝えるようにしましょう。
招待を伝える際の注意点
訃報を伝えることは、参列をお願いすることではありません。家族葬では、連絡を受けた人が参列すべきか迷うこともあるため、単に訃報を知らせるだけでなく「ぜひご参列いただきたい」といった明確な意志を添えましょう。
招待の有無や香典辞退などの意向をあいまいにしたままだと、相手に誤解を与えてしまい、後日トラブルに発展する可能性があります。連絡や会話のなかでは、感謝や配慮の気持ちを込めつつも、伝えるべきことは明確に伝える姿勢が大切です。
【遺族】参列者以外への連絡方法
家族葬は小規模で執り行うため、葬儀に招待しない方への対応も丁寧に行う必要があります。参列を辞退する旨をしっかりと伝えることで、相手に配慮の気持ちを示すとともに、不要な混乱を避けられます。
その際、故人の意思による小規模な家族葬であることや、遠方から来てもらうのは申し訳ない旨など、納得できる参列辞退の理由を添えるようにしましょう。
参列者以外には葬儀後に連絡する
家族葬に参列しない人への連絡は、葬儀が終わってからで構いません。無事に家族葬を終えたという報告とともに、故人が亡くなったことを伝えるのが一般的です。
電話だけでなく、ハガキや手紙による連絡でも問題ありません。会社の同僚やご近所の方、故人の友人・知人などには「本来であればご連絡すべきところでしたが、家族葬にて見送りました」という一文を添えると、相手も事情を理解しやすくなり、納得してもらえるでしょう。
葬儀前に連絡する場合の注意点
参列者以外であっても、葬儀前に訃報を知らせなければならない場合もあるでしょう。連絡する際は、以下の点に注意が必要です。
1点目は、参列辞退の旨を明確に伝えることです。「今回は家族葬のため、参列はご遠慮いただいております」とはっきり伝えることで、相手の誤解を防げます。日時や場所を記載しないことで、参列辞退の意思を伝えられるかもしれません。
2点目は、香典について知らせることです。香典や供花、供物を辞退する場合は、その意向も明確にしましょう。ご遠慮願いますと一言添えるだけで、問い合わせを回避し、遺族の負担が減らせます。
【遺族】家族葬の流れとポイント整理
家族葬の基本的な流れは一般葬と同じですが、招く人の範囲を限定する点が異なります。そのため、参列者の選定や連絡のタイミングが重要になります。ここでは、家族葬の全体像とともに、連絡や対応のポイントを整理しておきましょう。
①危篤・逝去
親族や関係者のなかでもとくに近しい人には、危篤の時点で迅速に状況を伝えましょう。最期の時間を過ごすためです。
逝去後には、家族葬で執り行うことを添えて、町内会や親しい友人などに伝える場合もあります。可能であれば、葬儀社に関する情報を収集したり、相談したりすることも検討するとよいでしょう。
②葬儀社との打ち合わせ
葬儀社と日程や内容、遺影、予算などを相談しながら決めます。この段階で、参列してもらう人の範囲を具体的に決め、リストアップを進めましょう。早めに決めることで、招待や辞退の連絡がスムーズに行えます。
③お通夜の準備
参列をお願いする人に対し、家族葬の日時や場所について伝えましょう。家族葬のように参列者が少ない葬儀であっても、弔問や供花への対応を想定して準備を整えることが大切です。
副葬品がある場合は、この段階で準備しておきましょう。棺に納められるか不安な場合は、葬儀社に相談しておくと安心です。
④通夜・告別式
葬儀・告別式は、故人と一緒にいられる最後の大切な場です。式の進行は葬儀社に任せ、故人を偲ぶことに集中し、参列者には丁寧に感謝の気持ちを伝えましょう。
葬儀後は、参列できなかった方々へ葬儀終了の報告を行い、香典返しや挨拶状の準備も進めます。葬儀社のサポートがある場合が多いため、相談することをおすすめします。
【参列者】家族葬の連絡はいつ来る?
家族葬では、遺族の意向により連絡のタイミングが一般葬と異なる場合があります。亡くなった当日や翌日に訃報が届くこともありますが、家族葬では遺族の判断で葬儀後に訃報を知らせるケースも珍しくありません。
連絡が遅れても、なぜ自分に連絡がこなかったのかと悩む必要はありません。遺族の「家族葬で送りたい」という事情を尊重し、落ち着いて受け止めましょう。遅くとも四十九日までに訃報の連絡があることが多いですが、ご家庭によってはさらに遅れることもあります。
連絡手段も多様化しており、対面や電話だけでなく、メールやSNSなどで訃報を受け取ることもあります。
【参列者】明確な招待がある場合のみ参列する
家族葬は、遺族が招待する人を限定して執り行う葬儀です。そのため、参列する際には明確な招待があったかどうかが最も重要な判断基準となります。たとえ故人と親しかった場合でも、遺族から直接の連絡や案内がなければ、参列を控えるのがマナーです。
人づてに訃報を聞き、最後のお別れをしたいと参列を希望するかもしれません。しかし、家族葬では、親族やごく親しい友人だけが招かれることが多いため、自己判断で参列するのは避けましょう。遺族の意向に反してしまうと、かえって負担や気遣いを強いることになりかねません。
訃報と招待を間違えないよう注意
訃報は亡くなったことを知らせるものであり、招待する意味を含んでいるわけではありません。とくに、家族葬の場合は「葬儀は親族のみで執り行います」などの文言が添えられていることも多く、これは参列をご遠慮いただきたいという意思表示です。
訃報連絡の際に参列辞退の旨の記載がなく、日時や場所の記載がある場合には、参列しても問題ない場合もあります。その場合は、事前に遺族の意向を確認したうえで参列するとよいでしょう。
【参列者】家族葬に参列する際のマナー
家族葬は、一般的な葬儀よりも規模が小さく、招かれた人だけで静かに執り行われる葬儀形式ですが、参列する際の基本的なマナーは変わりません。遺族の意向を尊重し、故人への敬意をもって行動することが大切です。
ここでは、家族葬に参列する際に知っておきたいマナーについて詳しく解説します。
服装
家族葬では、喪服や礼服が一般的です。男性なら黒のスーツに白いワイシャツと黒いネクタイ、黒い靴下と靴を合わせます。女性も黒のワンピースやスーツ、黒いストッキングとパンプスを選びましょう。
アクセサリーは真珠など控えめなものにし、派手なメイクや髪型、肌の露出は避けます。子どもを連れて参列する場合は、学校の制服や地味な色合いの服装を選ぶとよいでしょう。
香典
香典を持参するかどうかは、招待の際の案内や遺族の意向に従いましょう。香典辞退と明記されている場合は持参せず、辞退の表記がなければ通常どおり用意します。一般葬とは異なり、受付が用意されていない場合には、式場内や控室で渡すとよいでしょう。
香典は、一般的に関係性が近ければ近いほど、包む金額が大きくなるという慣習があります。家族葬であっても、その傾向は変わりません。友人として家族葬に参列する場合は、5,000〜10,000円程度が目安です。
供花・供物
供花や供物も香典と同様に、まずは遺族のご意向を確認してから送るのが望ましいとされています。家族葬では会場のスペースに限りがある場合も多いため、事前の確認をせずに送ってしまうと、対応にご負担をかけてしまうこともあります。
供花や供物を送る際は、葬儀社を通じて手配するのが一般的です。遺族の意向がわからない場合には、葬儀社に確認してみましょう。供物にメッセージカードを添える場合は、故人への感謝や哀悼の意を伝えるようにしましょう。
弔電
遠方に住んでいるなど、やむを得ない事情で葬儀に参列できない場合には、弔電を送ることで哀悼の意を伝えられます。弔電は多くの場合、葬儀社を通じて手配でき、葬儀当日に会場へ届けてもらうことが可能です。
文面はできるだけ簡潔にまとめつつも、故人への敬意や遺族への配慮が伝わるよう心がけましょう。また、忌み言葉や不吉な連想を避けた表現を用いることが大切です。
形式的でも構いませんが、できるだけ気持ちを込めた言葉を選ぶと印象がよくなります。
お悔やみの言葉
遺族と対面した際は、丁寧なお悔やみの言葉を述べましょう。代表的な表現としては「このたびはご愁傷さまでございます」や「心よりお悔やみ申し上げます」などがあります。
一方で「重ね重ね」や「たびたび」などの繰り返し言葉は、不幸が続くことを連想させるため、避けるのがマナーとされています。声をかけるタイミングや話し方にも気を配り、遺族の心情に寄り添う姿勢を忘れないようにしましょう。
招待されていない人は誘わない
家族葬は、あらかじめ招待された人だけで執り行われるため、自分が招かれていても、知人や家族などを帯同させるのはマナー違反です。
参列の対象は、あくまで直接連絡を受けた個人です。連絡を受けた人のみの参列が好ましいですが、どうしても帯同したい人がいる場合には事前に必ず遺族の了承を得ましょう。
【参列しない人】家族葬に参列しない場合のマナー
家族葬は、遺族が招いた限られた人だけで行う葬儀です。そのため、たとえ故人と親しい関係であっても、招かれなかった場合は参列を控えるのが基本です。
しかし、参列しなくても故人を偲び、遺族に心を寄せる方法はあります。ここでは、家族葬に参列しないときのマナーを解説します。
香典・供花・供物・弔電は遺族の了承を得てから
家族葬では「香典や供物はご遠慮ください」と明記されることがあります。そのような場合は、無理に送ることは控えましょう。
どうしても気持ちを伝えたい場合には、まず遺族に確認を取ることが必要です。了承を得たうえで、適切な時期と方法で香典や弔電、供花などを送るようにしましょう。
お悔やみの連絡は葬儀が終わってから
葬儀前は遺族にとって大切な準備の時期でもあり、さまざまな対応に追われていることが多いものです。そのため、急な連絡は控え、タイミングを見計らうことが望ましいです。
家族葬では、参列者のご案内や式の準備などを限られた人数で行っている場合もあります。遺族のご負担を思いやる意味でも、葬儀が終わって気持ちが少し落ち着いた頃に、改めて連絡するのが丁寧な対応です。
お悔やみの気持ちを伝える際は、電話にこだわらず、手紙やメールなど、相手のご都合に配慮した方法を選ぶとよいでしょう。
葬儀後の弔問は遺族に確認を取ってから
どうしても故人に手を合わせたいという場合は、葬儀後に弔問を希望することもあるでしょう。その場合も事前に遺族に確認を取り、訪問の日時を相談することが重要です。
突然訪問するのは控え、弔問の意思を伝える際も「ご迷惑でなければ」といった配慮ある言葉を添えるとよいでしょう。
遺族が本心では断りたい場合も、香典を渡したいと強く申し出ると断りにくくなってしまいます。遺族の状況を優先してもらうために、一歩引いて伝えるとよいでしょう。
メモリードのお葬式では、東京・埼玉・群馬の葬儀場・斎場の検索が可能です。 ご要望に応じた料金プランなどの相談も受け付けております。 お困りの際にはぜひお問い合わせください。
まとめ
家族葬は、どこまで呼ぶか、呼ばないかの判断に悩みが生じやすい形式です。しかし、範囲の決め方や連絡の方法、参列時や参列しない場合のマナーを知っておくことで、心のこもった見送りが可能になります。
故人の想いや遺族の意向を大切にしながらお見送りができると、故人にとっても遺族にとっても納得のいく家族葬になるでしょう。
メモリードのお葬式では、お客様のご要望に応じたさまざまな葬儀プランをご提案しています。217名の一級葬祭ディレクターが、事前相談から葬儀後のアフターサポートにいたるまで、幅広く対応しており、安心してお任せいただけます。
無料相談も承っておりますので、故人との最後のお別れを納得のいく形で迎えたいとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。