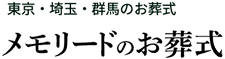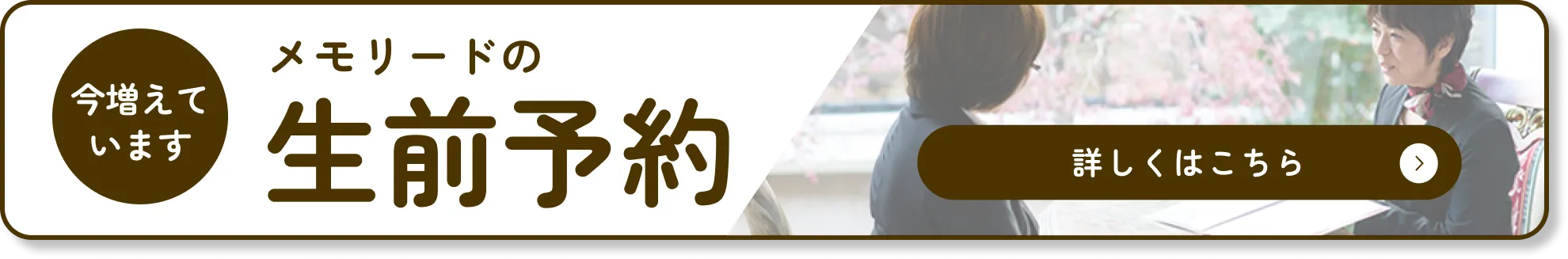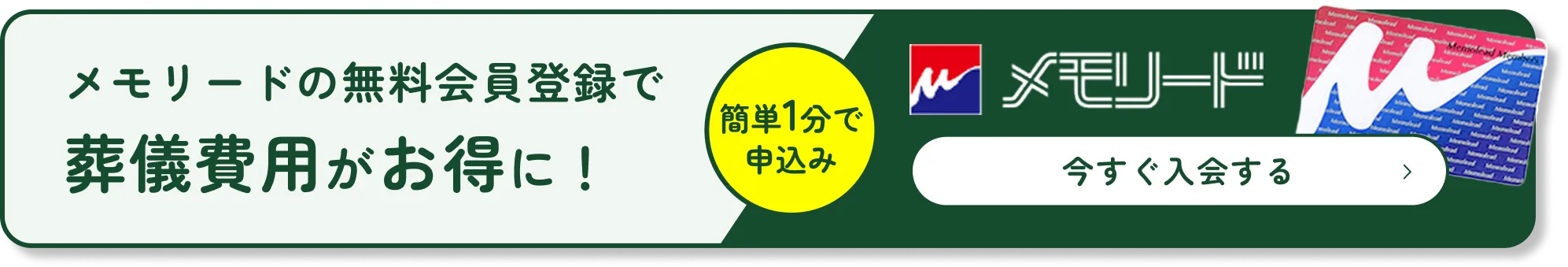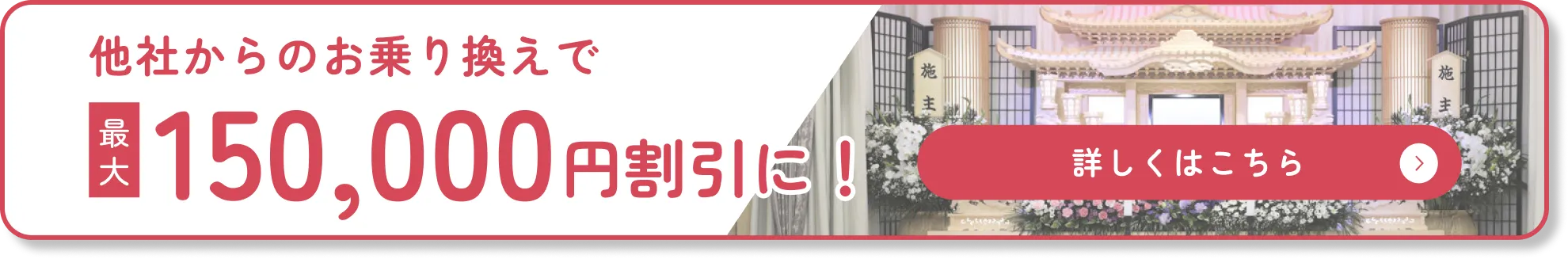親しい方が突然亡くなられたとき、悲しみのなかでも会社への連絡や葬儀の準備など、やるべきことは数多くあります。そんなときに活用できるのが「忌引き休暇」です。
しかし、忌引き休暇は法律で定められた制度ではなく、企業独自の福利厚生として設けられているため、取得できる日数や対象範囲は会社によって異なります。いざというときに慌てないよう、事前に制度の内容を理解しておくことが大切です。
この記事では、忌引き休暇の基本的な知識から対象となる親族の範囲、取得日数の目安、申請の方法、注意点まで、わかりやすく解説します。大切な方を安心して送り出すための準備として、ぜひ最後までお読みください。
忌引き休暇とは?
忌引き休暇とは、家族や親族が亡くなったときに、葬儀の準備や告別式への参列、必要な手続きを行うために取得できる休暇制度です。会社によっては「慶弔休暇」や「服喪休暇」と呼ばれる場合もありますが、目的は同じです。
ここで覚えておきたいのは、忌引き休暇が法律で定められた制度ではないという点です。労働基準法などの法令で義務づけられているわけではなく、企業が独自に設けている福利厚生のひとつとして運用されています。そのため、制度の有無や内容、日数などは会社ごとに異なります。
厚生労働省の調査によると、忌引き休暇制度を設けている企業は全体の約96%にのぼります。1回あたりの平均付与日数はおよそ5日間とされています。
出典:厚生労働省 慶弔休暇について(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020thx-att/2r98520000020tmf.pdf)
パートは企業によって異なる場合がある
正社員だけでなく、パートタイム労働者やアルバイトの方が忌引き休暇を取得できるかどうかは、会社ごとの就業規則によって異なります。
2020年4月に導入された「同一労働同一賃金制度」では、厚生労働省のガイドラインにおいて、短時間勤務や有期雇用の労働者にも、正社員と同等の慶弔休暇を付与することが「望ましい」とされています。これは努力義務であり、法的な強制力があるわけではありません。
そのため、実際には正社員のみが対象となる企業も少なくありません。勤務時間や勤続年数などの条件によって、休暇が認められるかどうかが変わる場合もあります。
契約社員や派遣社員の場合も同様です。契約社員は勤務先の就業規則に、派遣社員は派遣元である派遣会社の規定に従うことになります。いざというときに慌てないよう、あらかじめ自分の雇用形態と勤務先のルールを確認しておくことが大切です。
忌引き休暇の対象範囲と取得可能日数
忌引き休暇の対象となる親族の範囲は、一般的に3親等までとされています。
ここで注意したいのは、配偶者は血のつながりではなく婚姻による法的な関係であるため、親等には含まれないという点です。ただし、忌引き休暇の対象としては最も日数が長く設定されるのが一般的です。
故人との関係による、主な取得日数の目安は次のとおりです。
| 0親等 | 配偶者:7~10日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1親等 | 父母(実父母):5~7日 | 義父母:3~5日 | 子ども:5~7日 | |
| 2親等 | 祖父母:3~5日(別居3日程度、同居5日程度) | 兄弟姉妹:3~5日 | 義祖父母:1~3日 | 孫:1日 |
| 3親等 | 曾祖父母:1日 | おじ・おば:1日 | 甥・姪:1日 |
これらはあくまで一般的な目安であり、実際の日数は企業によって異なります。とくに、喪主を務める場合や遠方での葬儀に参列する場合には、追加で休暇が認められることもあります。
また、3親等の親族、たとえばおじ・おば・甥・姪・曾祖父母などは、会社によっては対象外とされることもあります。
土日が含まれる場合
忌引き休暇の日数に、土日や祝日などの公休日が含まれるかどうかは、会社によって取り扱いが異なります。
多くの企業では「暦日ベース(カレンダー通り)」で日数を数えます。この場合、土日祝日も休暇期間に含まれます。たとえば、金曜日から3日間の忌引き休暇を取得した場合は、金・土・日の3日間が休暇となり、月曜日から通常勤務に戻ります。
一方で「出勤日ベース」で数える企業もあります。この場合、公休日を除いた出勤予定日だけが休暇としてカウントされます。たとえば、土曜日に亡くなった場合に3日間の休暇を取ると、月・火・水の3日間が忌引き休暇となり、木曜日から出勤する形になります。
どちらの方式を採用しているかは、就業規則に明記されています。
忌引き休暇と有休・公休の違い
忌引き休暇・有給休暇・公休は、いずれも仕事を休むための制度ですが、その性質や法律上の位置づけは大きく異なります。
まず「公休」とは、会社があらかじめ定めた休日のことです。一般的には土日や祝日が該当し、労働契約に基づいて設定されています。多くの場合は無給であり、勤務日には含まれません。
次に「有給休暇」は、労働基準法で定められた法定休暇です。一定の条件を満たした労働者には必ず付与され、取得理由を問わず自由に使うことができます。休暇中も給与が支払われる点が大きな特徴です。
一方で「忌引き休暇」は、法律で義務づけられたものではありません。企業が独自に設ける福利厚生制度のひとつで、内容や日数は会社ごとの裁量に委ねられています。取得できるのは、家族や親族など近しい人が亡くなった場合に限られます。
公務員は特別休暇扱いになる
公務員の場合、忌引き休暇は「特別休暇」として位置づけられ、所属する自治体の条例や規則によって定められています。
たとえば配偶者や父母の場合は7日間、祖父母や兄弟姉妹の場合は3日間といったように、関係性ごとに明確な日数を定めているケースが一般的です。
忌引き休暇はいつから取得できる?
忌引き休暇がいつから始まるのか、その「起算日」は企業によって取り扱いが異なります。
もっとも一般的なのは「故人が亡くなった当日」または「翌日」から起算するパターンです。なかには、死亡日当日を1日目とする会社もあれば、翌日から数える会社もあります。
一方で「亡くなった事実を知った日」から起算する企業もあります。これは、遠方に住む親族の訃報がすぐに届かない場合などを考慮したルールです。また「通夜の日から」休暇を始めるケースや「葬儀の日を含む前後の期間」で設定する企業もあります。
このように、起算日の考え方は会社によってさまざまです。遠方での葬儀や、火葬場の混雑によって通夜や葬儀が遅れる場合は、規定の日数では足りないこともあります。そんなときは、早めに上司へ相談し、追加の休暇や有給休暇との併用を検討することをおすすめします。
忌引き休暇を取得する場合の給料は?
忌引き休暇中に給与が支払われるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。忌引き休暇は法律で義務づけられたものではないため、給与の扱いも企業の裁量に委ねられているのです。
一般的には、次の3つのパターンに分かれます。
・パターン1:有給扱い(通常出勤と同様に給与を支給) 年次有給休暇とは別に「特別休暇」として設定され、休暇中も給与が全額支払われます。多くの企業がこの方式を採用しています。
・パターン2:無給扱い(出勤扱いだが給与は支払われない) 出勤日数には含まれますが、給与は発生しません。ただし、皆勤手当などには影響しない場合もあります。
・パターン3:欠勤扱い(給与は支払われない) 完全に欠勤として扱われ、給与は支給されません。この場合、年次有給休暇を併用するよう推奨する企業もあります。
また、基本給のみ支給し、各種手当は対象外とする企業もあります。
忌引き休暇の取得方法
忌引き休暇を円滑に取得するためには、適切な手順を踏むことが大切です。急な出来事で気持ちが動転しているなかでも、以下の流れに沿って進めることで、スムーズに休暇を取得できます。
①直属の上司へ速やかに連絡する
忌引き休暇を取得する際は、まず最初に直属の上司へ連絡します。連絡方法は、口頭もしくは電話が基本です。早朝や深夜など電話が難しい時間帯であれば、まずメールで第一報を入れておき、連絡が可能になった時点で改めて口頭で伝えるようにしましょう。
このときに伝えるべき主な内容は次のとおりです。
・亡くなった方との続柄(例:実父、祖母など)
・希望する休暇期間(何日から何日まで)
・通夜や葬儀の日程(決まっていれば)
・葬儀会場の名称と場所(決まっていれば)
・休暇中の緊急連絡先
会社によっては、上司や同僚が葬儀に参列したり、弔電・供花を送ったりすることがあります。そのため、できるだけ早く、分かる範囲で詳細を伝えるのが望ましいです。
また、家族葬など親族のみで執り行う場合は「親族のみの家族葬で執り行う予定です」と一言添えると、会社側も対応しやすくなります。
②メール等で詳細を報告する
口頭での連絡後、または口頭での連絡が難しい場合は、メールで詳細を報告します。メールは記録として残るため、後々の確認にも役立ちます。
ただし、メールのみで済ませるのは避けましょう。必ず口頭でも伝える、あるいはメール送信後に改めて電話やオンラインで報告することが、社会人としてのマナーです。
③業務の引き継ぎを行う
休暇中に業務が滞らないよう、同僚や後輩への引き継ぎをしっかり行いましょう。引き継ぎ内容はメールで残しておくと、認識のズレや作業漏れを防ぐことができます。
引き継ぎを行う際は「いつまでに、何をしてほしいのか」を具体的に伝えることが大切です。休暇中に顧客との打ち合わせや重要な商談が予定されている場合は、キャンセルや日程変更の連絡も早めに行いましょう。もし自分で対応できない場合は、上司や同僚に代わりの連絡をお願いしておくと安心です。
また、取引先への連絡も忘れずに行い、休暇中の対応体制を明確にしておくことで、ビジネス上のトラブルを防ぐことができます。
メールで連絡するときの例文
メールで忌引き休暇を連絡する際は、件名で用件が分かるようにし、必要な情報を簡潔に記載することが重要です。
会社の場合
件名:忌引き休暇取得のご連絡
○○部長
お疲れ様です。○○(氏名)です。 このたび、実父が○月○日に逝去いたしました。 急なご連絡となり大変恐縮ですが、忌引き休暇を取得させていただきたく、メールにてご連絡申し上げます。
【休暇期間】○月○日(月)~○月○日(水)までの3日間
【通夜・葬儀の日程】
通夜:○月○日(月)午後6時より
葬儀・告別式:○月○日(火)午前11時より
【葬儀会場】○○斎場(住所:〒xxx-xxxx ○○県○○市○○町x-x-x)
【休暇中の緊急連絡先】090-xxxx-xxxx
なお、親族のみの家族葬にて執り行う予定です。 現在担当している業務につきましては、○○さんに引き継ぎを依頼済みです。 ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
署名
学校の場合
学校への連絡は、小中高生の場合は保護者が担任の先生に行うのが一般的です。大学生の場合は、本人が学生部や学務課などに連絡します。
件名:忌引き休暇のご連絡(○年○組 ○○)
○○先生
お世話になっております。 ○年○組 ○○の保護者、○○でございます。 このたび、子どもの祖母(私の実母)が○月○日に逝去いたしました。 つきましては、下記の期間、忌引き休暇を取得させていただきたく存じます。
【休暇期間】○月○日(月)~○月○日(水)
【通夜・葬儀の日程】
通夜:○月○日(月)午後6時より
葬儀:○月○日(火)午前10時より
【緊急連絡先】090-xxxx-xxxx
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
保護者氏名
忌引き休暇を取得するときの注意点
忌引き休暇をスムーズに取得し、周囲への負担を最小限に抑えるためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。
就業規則を確認する
忌引き休暇は企業独自の制度であるため、取得できる日数や対象となる親族の範囲、必要書類、申請方法などは、すべて会社ごとの就業規則で定められています。
とくに、次の点をチェックしておくと安心です。
・対象となる親族の範囲
・続柄ごとの取得可能日数
・起算日
・土日祝日の扱い
・給与の支払い有無
・申請に必要な書類
・遠方での葬儀や喪主を務める場合の特別規定
就業規則の内容が分かりにくい場合は、人事担当者に確認しておきましょう。
申請は速やかに行う
身内に不幸があった際は悲しみのなかでも、できるだけ早く会社に連絡することが重要です。
早めに連絡することで、業務の引き継ぎがスムーズに進み、周囲の同僚も対応しやすくなります。また、会社側も弔電や供花の手配、上司の参列準備などを適切に進めることができます。
連絡が遅れると、緊急の案件への対応が遅れたり、取引先に迷惑をかけたりする可能性もあります。つらい状況ではありますが、速やかな連絡を心がけましょう。
必要書類を用意する
会社によっては、忌引き休暇取得後に、休暇の事実を証明する書類の提出を求められる場合があります。
重要なのは、これらの書類は公的な証明書ではなく、あくまで忌引き休暇を裏付けるための書類であるという点です。忌引き休暇の証明として一般的に使われる書類は、以下のとおりです。
死亡診断書
死亡診断書は、医師が故人の死亡を証明する書類で、最も直接的な証明書類です。ただし、原本は各種手続きに必要となるため、会社に提出する際はコピーを用意するのが一般的です。
火葬許可証・埋葬許可証
火葬許可証や埋葬許可証も、故人の火葬や埋葬が行われたことを証明する書類として使えます。これらもコピーでの提出が一般的です。
葬儀証明書
葬儀証明書は、葬儀社が発行する、葬儀を執り行ったことを証明する書類です。一般的に、故人の氏名、喪主名、葬儀の日時、葬儀場名、葬儀社名などが記載されています。
メモリードのお葬式でも葬儀証明書の発行に対応しております。忌引き休暇の証明書類が必要な場合は、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧にサポートいたします。
葬儀案内はがき
葬儀の案内はがきも証明書類として認められる場合がありますが、これは故人が亡くなったことや葬儀日時を通知する文書に過ぎず、確実な証明書とは言えません。
会社や学校によっては認められない可能性もあるため、できる限り死亡診断書のコピーや葬儀証明書など、より確実性の高い書類もあわせて用意することをおすすめします。
どの書類が必要かは会社の就業規則に記載されているか、人事部門に問い合わせることで確認できます。休暇明けにスムーズに提出できるよう事前に確認し、不備なく準備しておきましょう。
業務の引き継ぎをしっかり行う
忌引き休暇中に業務が滞ると、取引先や同僚に負担をかけてしまうことがあります。休暇前に、しっかりと引き継ぎを行いましょう。
引き継ぎ内容はメールで共有し、記録として残しておくと安心です。後から確認する際にも役立ちます。
忌引きを使わなかった場合も連絡する
申請した忌引き休暇を、何らかの理由で使わなかった場合や、予定より早く復帰できる場合も、必ず上司に連絡しましょう。
たとえば、当初3日間の休暇を申請したものの、葬儀の日程が早まり2日間で済んだ場合などは、その旨を報告します。これは、業務の引き継ぎを受けた同僚への配慮でもあり、職場の混乱を防ぐためにも重要です。
忌引き休暇中の過ごし方
忌引き休暇中は、通常の休暇とは過ごし方が異なります。故人を悼み、心を落ち着かせるための期間として、適切に過ごすことが大切です。
忌中に避ける行動
「忌中(きちゅう)」とは、身内が亡くなってから四十九日法要を迎えるまでの期間を指します。この期間は、故人の冥福を祈り、静かに喪に服す時期とされています。
一般的には、忌中の間に次のような行動を控えるのがマナーです。
・慶事への参加
・派手な娯楽やレジャー
・神社への参拝
・新年のお祝い
ただし、近年は家族葬が増えるなど、葬儀の形式や考え方も多様化しています。地域や宗教、家庭によって慣習が異なるため、周囲の意向を尊重しながら柔軟に対応することが大切です。
日常生活での配慮
忌引き休暇中は、できるだけ静かに過ごし、故人を偲ぶ時間を大切にしましょう。家族と共に過ごし、思い出を語り合うことで、心の整理がつきやすくなります。
葬儀後には、香典返しの準備や、各種手続き(銀行口座の解約、年金の停止手続き、保険金の請求など)も必要になります。これらの手続きには時間がかかることも多いため、計画的に進めることが大切です。
友人などからの誘いを断る
忌引き休暇中に友人から食事や遊びの誘いを受けることもあるかもしれません。そのような場合は、丁寧に事情を説明して断りましょう。
「この度、身内に不幸がございまして、しばらくは控えさせていただきます。落ち着きましたら、改めてご連絡させてください」といった形で相手に不快感を与えず、自身の状況を理解してもらうことが大切です。
祭壇へお供えをする
故人の供養として、自宅に設けた祭壇へお供えをすることも大切な過ごし方のひとつです。
祭壇は「中陰壇」や「後飾り」と呼ばれることもあり、故人の遺骨を安置する目的があります。極楽浄土へ行けることを願い、水や線香、また故人が好きだった食べ物や花を供え、手を合わせることで、心の整理がつきやすくなります。
四十九日法要の準備をする
忌引き休暇期間中に、落ち着いたタイミングで四十九日法要の準備を少しずつ進めることも必要です。法要の日程調整、会場の手配、案内状の作成など、やるべきことは意外と多いものです。
ただし、喪主ではない場合は、具体的な準備を自分で行う必要はありません。喪主やほかの親族と相談しながら、必要に応じてサポートする形で十分です。
忌引き明けにすべきこと
忌引き休暇を終えて職場に復帰する際には、いくつか心がけるべきマナーがあります。
休暇明けの挨拶
職場に復帰した初日には、休暇中に業務をサポートしてくれた上司や同僚、部下へ個別に挨拶し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
「この度は急な休暇をいただき、ご迷惑をおかけいたしました。おかげさまで無事に葬儀を終えることができました。ありがとうございました。」といった簡潔な言葉で十分です。
また、復帰後は休暇中の業務状況を確認し、引き継いだ仕事に問題がなかったか、対応が必要な案件が残っていないかをチェックしましょう。
香典返しを渡す
会社や個人から香典をいただいた場合は、適切なタイミングで香典返しをお渡しするのがマナーです。一般的には、四十九日法要を終えた後に贈るのが慣例ですが、会社の方針や地域の風習によって異なることもあります。
香典返しの品としては、お茶や海苔、タオル、洗剤など「食べたり使ったりしてなくなるもの」つまり「不祝儀を残さないもの」がよいとされています。
また、会社から香典をいただいた場合は、個別に贈るのではなく、部署全体で分けられるお菓子などを用意するのもひとつの方法です。
忌引き休暇の取得率
厚生労働省の調査によると、忌引き休暇を含む慶弔休暇制度を設けている企業は多く、労働者が30人以上いる民営企業のうち、96.1%が忌引き休暇制度を導入しています。
また、企業規模が大きくなるほど実施率も高まる傾向があります。従業員数が1000人以上の企業では、本人の祖父母が亡くなった場合の慶弔休暇の実施率が95.1%に達しています。
一方で、パートタイム労働者への慶弔休暇の付与状況は、企業規模によって差があります。1000人以上の大企業では実施率が71.9%と比較的高いのに対し、30〜99人規模の中小企業では51.9%にとどまっています。
出典:厚生労働省 慶弔休暇について(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000020thx-att/2r98520000020tmf.pdf)
忌引き休暇でよくある質問
忌引き休暇について、読者の方々が抱きやすい疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1.祖父母が亡くなった場合は何日休める?
A. 祖父母が亡くなった場合の忌引き休暇は、一般的に3~5日程度が目安とされています。
ただし、同居していたかどうかで日数が変わるケースも多く、別居していた祖父母の場合は3日程度、同居していた祖父母の場合は5日程度と設定する企業もあります。
Q2.四十九日でも取得できますか?
A. 忌引き休暇は、一般的に葬儀や告別式への参列を主な目的としているため、四十九日法要のために忌引き休暇を取得することは難しいケースが多いです。
多くの企業では、四十九日法要などの法要については、通常の有給休暇を利用するか、企業が別途設けている「特別休暇」がある場合にそれを利用することになります。
Q3.ペットも対象になる?
A. 一般的に、忌引き休暇は家族や親族の死に際して取得するものであるため、ペットの死は対象外となります。
ただし、近年はペットを家族と考える方も増えており、一部の企業では「ペットロス休暇」などの独自の福利厚生を設けるケースも出てきています。
Q4.遠方での葬儀の場合、追加の取得はできる?
A. 遠方での葬儀の場合、移動時間が忌引き休暇に含まれないことが多いため、規定の日数では足りなくなる可能性があります。
そのような場合は、上司に相談して休暇期間の延長が可能か確認するか、有給休暇と組み合わせて対応することをおすすめします。
Q5.忌引き休暇中でも業務の連絡は必要?
A. 忌引き休暇中は故人を悼むことに専念する期間であり、業務連絡は最小限に留めるべきです。
事前に業務の引き継ぎをしっかり行っておくことで、会社からの不要な連絡を減らすことができます。ただし、緊急時のために連絡先は会社に伝えておくことをおすすめします。
Q6.忌引き休暇制度のない会社もある?
A. 忌引き休暇は法律で義務付けられた休暇ではないため、制度を設けていない会社も存在します。
厚生労働省の調査では、96.1%の企業が制度を導入していますが、残りの約4%の企業には制度がないということになります。
忌引き休暇制度がない会社の場合、有給休暇を使って休む、あるいは欠勤として扱われることになります。
まとめ
忌引き休暇は大切な方を亡くされた際に、葬儀の準備や参列、そして心の整理をするために取得できる制度です。法律で定められたものではなく、企業が独自に設ける福利厚生のひとつであるため、取得日数や対象範囲、給与の扱いなどは会社によって異なります。
いざというときに慌てないためには、あらかじめ就業規則を確認し、取得方法や必要書類を把握しておくことが大切です。
メモリードのお葬式では、関東エリアを中心に、ご家族の想いに寄り添った質の高い葬祭サービスを提供しています。厚生労働省認定の一級葬祭ディレクターが在籍し、事前相談から当日の進行、四十九日法要などのアフターサポートまで、丁寧にお手伝いいたします。
突然のご不幸への対応はもちろん、事前のご相談も随時承っております。さらに、仏壇・仏具、墓地・墓石、遺品整理など、葬儀後のさまざまなご相談にも対応しております。
大切な方を心を込めてお見送りし、ご遺族が穏やかな気持ちで故人を偲べるように、メモリードのお葬式が誠意をもってサポートいたします。
メモリードのお葬式では、一日葬のプランをご提案可能です。 全国210の施設でご葬儀や事前相談を受け付けております。 お困りの際にはぜひお問い合わせください。