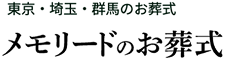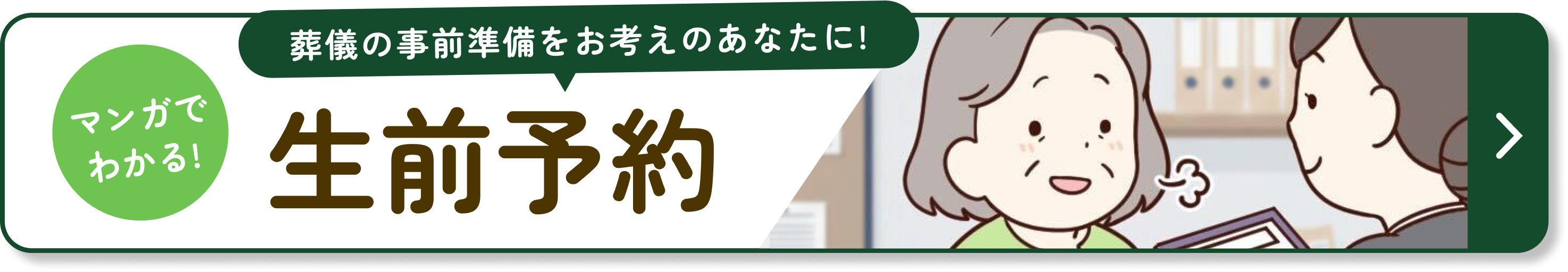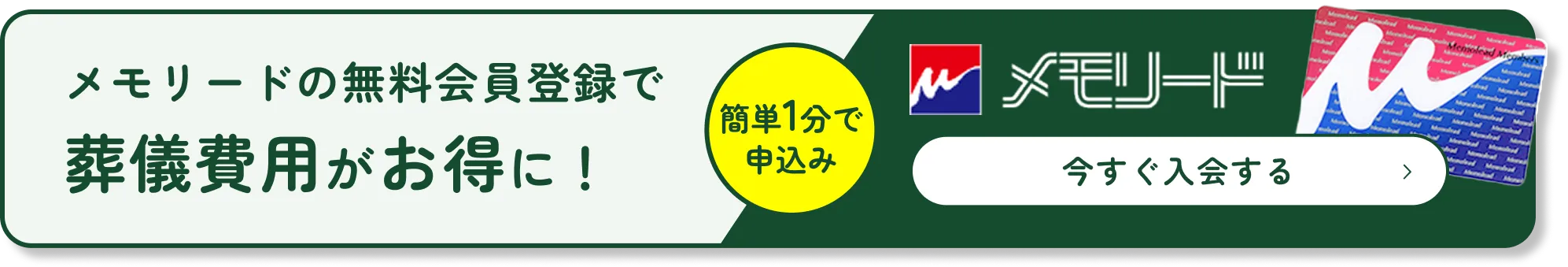告別式にかかる時間は、平均で1時間〜2時間ほどです。告別式に参列する予定がある方は、開始時間と終了時間も把握して、告別式に備えて準備しましょう。
本記事では、告別式にかかる時間をはじめ、開始時間や終了時間、大まかな流れをご紹介します。そのほか、参列する際の注意点やマナーもお伝えするため、失礼のないように参列したい方はぜひ参考にしてください。
告別式の時間
告別式に参列する予定がある方のなかには、どれくらいの時間がかかるか気になる方がいるでしょう。ここでは、告別式にかかる時間について、所要時間や開始時間、終了時間をご紹介します。
所要時間
告別式の所要時間は、受け付けを開始してから出棺まで1時間〜2時間ほどが平均です。ただし、遺族や参列者の人数で所要時間が変わるため、どれくらいの時間がかかるか把握する際の参考にしましょう。
告別式と火葬の時間を含めると、5時間〜6時間ほどかかるケースがあります。告別式の途中でトイレ休憩に行かなくてはいけない事態を避けたい場合は、所要時間を把握したうえで開式する前にトイレを済ませましょう。
開始時間
告別式の開始時間は、午前10時〜11時ごろの午前中が一般的です。ただし、火葬の時間や喪主・遺族の都合によって、開始時間が前後することもあります。一般的な葬式では、1日目にお通夜、2日目に告別式と火葬を行います。火葬に時間がかかるため、告別式は2日目の午前中に行われるケースが多いです。
告別式に遅れないためにも、開始時間を正確に把握し、前もって家を出るようにしましょう。
終了時間
告別式の終了時間は、12時ごろが目安です。告別式は、ほとんどが午前中に終わります。ただし、告別式の所要時間や開始時間によって予定よりも時間が多少ズレるケースがあります。
告別式の流れ
告別式に参列する方は、当日に慌てないように事前に流れを把握しておきましょう。地域によっては、流れが一部異なるケースがあります。ここでは、告別式の大まかな流れを11個の見出しに分けてご紹介します。
1.遺族集合
告別式当日は、開式の1時間〜2時間ほど前に喪主や遺族が集合するのが一般的です。遺族として告別式に参列するなら、開始時間よりも余裕を持って会場に集合するのが大切です。
喪主は、会場に着いたら動線やスケジュールを確認します。僧侶が会場に到着した際、喪主は挨拶をして迎え入れる対応も行う必要があります。
2.親族・受付係集合
喪主と遺族が集合したら、親族と受け付け係が会場に集合するのが一般的です。喪主と遺族の集合時間よりも少し遅く設定されているケースが多いですが、時間に遅れないように早めに到着するのがポイントです。
受け付け係を務める方は、会場に到着してから確認すべき項目や準備があります。参列者の人数が多く準備に時間がかかる場合は、受け付け係も喪主や遺族と同じ時間に集合すると時間に余裕ができるでしょう。
3.受付開始
受け付け係も集合し準備が整ったら、受け付けを開始します。受け付け係が参列者の対応を行い、喪主や遺族は参列者が見えたときに軽く挨拶するのがマナーです。
参列者と故人の話題で長話になる可能性がありますが、次々と参列者が訪れると長蛇の列ができてしまいます。参列者を迎え入れる際、芳名帳への記帳を促して香典を受け取り、御礼を渡すのが一連の流れです。
前日のお通夜で、すでに香典を受け取っている方は、芳名帳への記帳のみとなるため、受け付け係との情報共有が重要です。
また、少人数での葬儀を希望する場合は、受け付けを葬儀社のスタッフに任せられるケースがあります。受け付けでの対応や詳細は、事前に葬儀社と打ち合わせしておく必要があります。
4.遺族・参列者着席
受け付けが済んだら、遺族と参列者は着席します。着席する場所は、故人と関係性が深い方が前方、それ以外の知人は後方になります。喪主と遺族は最前列、続いて喪主の兄弟姉妹、配偶者などの親族が順番に着席するのが一般的です。
誰がどこに着席するか決められていないため、参列者の出欠状況や会場の規模に合わせて着席しましょう。どの列に座ればよいかわからないときは、喪主や遺族、受け付け係、近くにいる葬儀社のスタッフに聞くのが無難です。
5.開式・僧侶の入場
参列者が着席したら、司会が開式を宣言して告別式が開始されます。告別式が開式したら僧侶が入場しますが、喪主や遺族、参列者は着席したままで問題ありません。僧侶が一礼したときは、参列者も同じく一礼しましょう。
告別式の進行は、葬儀社のスタッフに任せられるため、基本的に指示に従うだけで問題ありません。喪主や遺族、受け付け係は、葬儀社のスタッフとの事前打ち合わせで流れを十分に把握しておくとよいでしょう。
6.弔事・弔電
弔辞や弔電が届いているときは、司会が読み上げます。喪主や遺族、参列者は、弔辞や弔電に対してそのまま耳を傾けるだけで構いません。
そもそも弔辞とは、告別式に参加できない方が贈る電報です。弔電とは、参列者が故人に贈るお別れの言葉です。すべてを読み上げるのは時間がかかるため、弔辞は読み上げずに弔電のみ読み上げるケースがあります。
弔電も多すぎるとすべてを読み上げるのは難しいため、時間の関係により数通を読み上げて、残りを名前のみ省略される場合があります。どの弔電を読むかは、事前に葬儀社スタッフと相談しておきましょう。
また、弔辞や弔電を読み上げたあとは、故人に関係のある音楽を流したり演奏したりするケースがあります。どのような音楽を流すか、事前に葬儀社のスタッフと打ち合わせして決めましょう。
7.お焼香
弔辞や弔電の読み上げ後、僧侶による読経が開始され、喪主や親族からお焼香を行います。僧侶による読経は30分〜40分ほどが一般的です。場合によっては、参列者にサッシを配って経文を一緒に声を出して読むケースがあります。
お焼香のやり方は宗派によって異なり、基本的に1回〜3回ほど行うケースがほとんどです。参列者が多いと1回、少人数だと2回〜3回ほどなど、参列者の人数や進行状況によって異なります。
お焼香の作法がわからないときは、喪主の動きをよく見て同じ動きをしましょう。お焼香の回数に指定があれば、葬儀社のスタッフや僧侶から指示される場合があります。
8.僧侶の退場
参列者全員がお焼香を終えたら、僧侶が退場します。その際、起立したり合掌したりしながら見送るのが一般的です。着席したまま見送るケースもありますが、葬儀社のスタッフや司会の指示を受けたり、周囲の状況に合わせたりするとよいでしょう。
9.花入れの儀
僧侶が退場したあとは、喪主や遺族を中心に花入れの儀を行います。花入れの儀とは、故人の棺のなかに花を入れて別れを告げる儀式です。お別れの儀とも呼ばれており、参列者で個人を囲って華やかに飾ってお別れを告げます。
故人と対面できるのは花入れの儀が最後であるため、お別れの言葉とともに感謝の気持ちも伝えましょう。花入れの儀の時間を十分に確保するために、弔辞や弔電を読み上げたりお焼香を行ったりする時間を抑えるケースがあります。
10.喪主の挨拶
花入れの儀が終わったら、喪主の挨拶を行います。喪主の挨拶では、遺族や参列者に感謝の気持ちを伝えるのが一般的です。挨拶の言葉はとくに決められていないため、喪主の素直な気持ちを伝えるとよいでしょう。
喪主と挨拶の代表者は、一致していなければいけないわけではありません。たとえば、喪主を配偶者が務めて、挨拶を子どもが行うケースがあります。挨拶のときは、冗長にならないように簡潔にまとめましょう。
11.閉式・出棺
喪主の挨拶が終わったら、閉式を宣言して出棺となります。出棺の際、棺の蓋を閉じて火葬場へ送り出します。霊柩車に遺族の手で納めたあとは、再度喪主が挨拶を行うのが一連の流れです。
霊柩車と遺族の移動手段が別々の場合、霊柩車の後を追うように遺族もバスで移動します。葬儀社によっては、霊柩車とバスが一体型になっているものがあり、故人と一緒に移動が可能です。
火葬にかかる時間は、1時間〜2時間ほどです。火葬中は控え室で待機し、精進落としの料理があればいただきます。生前の故人にまつわる会話をしながら、控え室で過ごすとよいでしょう。
告別式に参列する際の注意点
告別式に参列する際、大まかな流れに加え、いくつかある注意点も把握しましょう。ここでは、告別式に参列するときの注意点を3つご紹介します。
言葉遣いに気をつける
告別式での言葉遣いでは、避けるべき表現があります。死ぬ・死亡・急死などの死に直接的な表現は避けるべきです。表現を変えるときは「ご不幸」「突然のことで」などの表現を使うのがマナーです。
重ね重ね・ますますなどの繰り返しを表す言葉は、不幸が重なることを連想させます。遺族に挨拶する機会が複数回あっても、重ね重ねやますますなどの言葉を避けて挨拶しましょう。
また、声のトーンを抑えて挨拶をするのが決まりです。長々と続かないように、挨拶は「この度はご愁傷さまです」などと手短に済ませましょう。
時間に余裕を持って到着する
告別式の開始時間は決まっていますが、時間ギリギリにならないように、余裕を持って到着しましょう。受け付けでは、挨拶したり香典を渡したりといくつか工程があるため、参列者が多い場合を考慮して早めに出発するのが無難です。
予定どおり到着するのを想定していても、場所や日時をしっかり把握していなければ遅れるおそれがあります。仕事や交通状況により遅れてしまうときは、読経やお焼香が行われている途中で入場する可能性が高いです。
遅れる可能性が高い場合、喪主や遺族に直接電話しないようにしましょう。会場で電話が鳴り響くのを避けるために、葬儀場へ連絡するのがマナーとなります。
また、お通夜や告別式は急なお知らせとなるケースがほとんどであるため、すでに予定が入っていて遅れる可能性がある方もいるでしょう。遅刻するのが確定していれば、葬儀が開始される前に電話で伝えておくとよいでしょう。
参列できない場合の対応方法を考える
遠方に住んでいる方や当日体調不良になった方は、参列できないときの対応を取ることが大切です。やむを得ない事情で告別式に参列できなくても、遺族に弔意を伝えましょう。
自分以外に代わりに告別式に参列できる人物がいれば、代理人を立てます。遠方に住んでいて参列できないのが前もってわかっている場合は、香典やお供えの品を送ったり、弔電を打ったりするとよいでしょう。
参列できないことに対する謝罪と、故人への追悼の意を伝えるのはマナーです。後日弔問に伺えるなら、挨拶状を一緒に送るとともに、あらためて後日挨拶する旨を伝えておきましょう。
告別式に参列する際のマナー
告別式への参列が決まったら、服装やお焼香などのマナーを把握しておく必要があります。無礼なく故人への追悼の意を伝えられるように、告別式におけるマナーを確認しておきましょう。ここでは、告別式に参列するときのマナーを5つご紹介します。
連絡のマナー
告別式は午前中や日中に行われるケースがほとんどであるため、会社を休まなければいけないなら、早めに会社に連絡する必要があります。遺族として葬儀に参列する際、忌引き休暇を取得するのが一般的です。
連絡方法は基本的に電話ですが、夜間ならメールで連絡した翌日にあらためて電話で連絡しましょう。やむを得ない理由であるものの、急に仕事を休むことになるため、今後の会社の人間関係への影響を考慮してしっかり連絡するのがマナーです。
忌引き休暇を取得する場合、故人との関係で休暇日数が異なるため、会社に誰の葬儀に参列するかも伝えましょう。勤務先の就業規則によって取得できる休暇日数が決まっていますが、3親等以上の親族の葬儀だと忌引き休暇の対象とはならないケースがあります。
また、危篤状態にある方がいれば、告別式を行うことが確定していなくても、上司に伝えておくとスムーズに対応してもらえます。忌引き休暇についても事前に説明を受けておくと安心です。
服装のマナー
告別式に参列する際、男女ともに喪服を着用するのがマナーです。具体的には、男性は黒色のスーツ、白色のシャツ、黒色のベルトやネクタイなどの小ものが一般的です。ビジネススーツは、喪服よりも光沢があり葬儀の場にはふさわしくありません。
女性は、黒色のスーツやアンサンブル、黒色のカバンや靴下などの小ものを揃えましょう。エナメル素材や革製品の小もの、派手なアクセサリー、露出の多い服装は避けるのがマナーです。
アクセサリーを着用する場合、イヤリングやピアスは真珠1粒で揺れないものにしましょう。ネックレスは、白色の真珠や黒真珠で一連になっているものを着用します。
時計は外しておくのが無難ですが、着用するならゴールドを避けるのがマナーです。結婚指輪は基本的に着用して問題ありませんが、気になるなら外しておきましょう。
喪主や遺族は正式礼装、一般参列者は準礼服や略喪服を着用します。男女ともにカジュアルな印象にならないようにしましょう。
持ち物のマナー
告別式への参列で準備すべきものは、香典や数珠、お供え用のお菓子などです。告別式に持っていく香典は、結び切りの水引きの不祝儀袋に包むのが一般的ですが、不祝儀袋を選ぶときは宗教に合わせましょう。
結び切りの水引きには、1度結んだらほどけないように、つまり不幸が繰り返されないようにという意味合いがあります。表書きには御香典やご香料と記入しますが、宗教がわからないときは御霊前と書くと無難です。
浄土真宗の場合は、表書きに御仏前と記入しましょう。告別式の前日にお通夜に参列する際、お通夜のタイミングで香典を渡すのがマナーとなっています。告別式のみに参列する方は、告別式当日でも問題ありません。
香典袋に新札を入れると、不幸を想定して準備していたと、とらえられてしまいます。無礼にあたってしまう可能性があるため、ある程度使用感のあるお札を用意して香典袋に入れましょう。
また、数珠は仏式の葬儀に参列する際に必要です。数珠の形や色は宗派によって異なりますが、わからないときは自分の宗派に合わせましょう。
葬儀中は左手首にかけておき、お焼香や挨拶で歩く際は左手で持つときに房を下にするのが一般的です。お焼香を行うときは、親指と人差し指の間に数珠をかけて合掌します。
お供え用に持っていくお菓子は、故人と親しい間柄なら用意するのが無難です。地域によっては葬儀にお菓子を持っていく風習があるため、事前に地域の風習を確認しておきましょう。
花や線香とともにお菓子を持っていくケースがあり、お菓子には必ず掛け紙をかけるのがマナーです。ただし、お供えものと区別したいお菓子は、掛け紙をかけないようにしましょう。お菓子選びでは、小分けになっており日持ちするものを選ぶと喜んでもらえます。
故人と慣れ親しんでいた方は、故人が生前に好んでいたお菓子を持っていくとよいでしょう。お供え用ではなく遺族に向けてお菓子を持っていくなら、遺族に配慮したお菓子選びが重要です。
焼香のマナー
お焼香のマナーは、宗派によって作法が異なります。天台宗・浄土宗・日蓮宗の場合、抹香を額の高さに上げて1回〜3回焼香します。真言宗は、抹香を額の高さに上げて3回焼香するのが正しい作法です。
曹洞宗の場合、1回目は抹香を額の高さに上げて、2回目にそのまま香炉にくべましょう。お焼香の際、故人の遺影や遺族に向かって礼をするのが一般的ですが、過度にしないように注意が必要です。
ただし、参列者が多い場合は、宗派や地域の慣習に関わらず、お焼香の回数を1回で済ませるように指示されるケースがあります。葬儀場のスタッフによりお焼香の回数を指定されたときは、故人の遺影や遺族への礼も長く時間をかけないようにしましょう。
出棺のマナー
告別式が閉式して出棺するとき、霊柩車が出発するまで静かに合掌するのがマナーです。合掌する際、故人に対して感謝の気持ちを込めて見送り、ご冥福を祈りましょう。
厳粛な雰囲気を保つために、私語を発するのは厳禁です。携帯電話が鳴り響くと厳粛な場が台無しになってしまうため、事前に携帯電話の電源を切る、またはマナーモードで音がならないようにしておきましょう。
出棺のときに限らず、受け付けする段階から携帯電話の音には注意が必要です。バイブ音でも周囲の方が気になってしまう可能性があるため、あらかじめ電源を切っておくと安心です。
精進落としのマナー
精進落としとは、故人の冥福を祈るとともに、喪主や遺族、参列者、僧侶に感謝の気持ちを示すために行われる会食です。告別式後に行われる会食であり、故人との思い出を振り返りながら食事するのが精進落としの役割となります。
精進落としでは、お酒を飲みすぎたり、大声で話さないようにするのがマナーです。故人とは関係のない話をするのも避けましょう。料理の片付けもあるため、長居せずに所定の時間内に食事を済ませるのがポイントです。
まとめ
告別式は、午前中から日中にかけて、1時間〜2時間ほど行われるケースがほとんどです。参列者の人数や地域の慣習によっては、告別式の時間帯や所要時間が異なるケースがあります。
告別式に参列する方は、服装やお焼香、精進落としなどのマナーを確認しておくことが重要です。厳粛な場であるため、言葉遣いにも気をつける必要があります。参列できない場合は、代理人を立てたり弔電を打ったりするなど、対処するのがマナーです。
メモリードのお葬式では、厚生労働省認定の一級葬祭ディレクターが葬祭をサポートいたします。葬儀の事前相談をはじめ、葬儀後のアフターサポートも対応可能です。故人の意思を汲み取った葬儀を行いたい方や葬儀内容にこだわりたい方は、ぜひご相談ください。
メモリードグループでは、東京・埼玉・群馬の斎場・葬儀場選びをサポートします。 公式サイトでは地域別に検索ができます。 お困りの際にはぜひご利用ください。