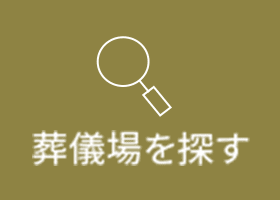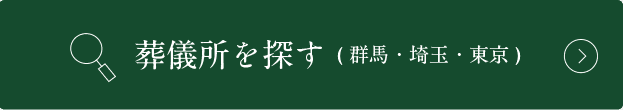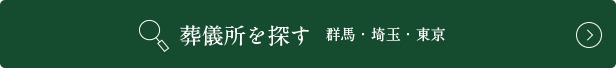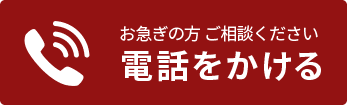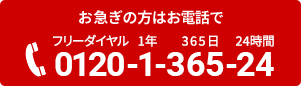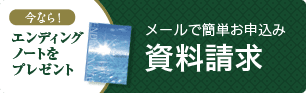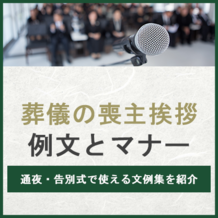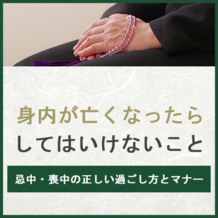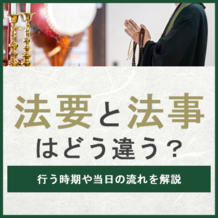大切な方を亡くした悲しみは、時間が経っても簡単には癒えるものではありません。故人を身近に感じながら、日々の暮らしの中で偲びたいと願う方が増えています。
そんな想いに応える供養の形が「手元供養」です。手元供養は、遺骨の全部または一部を自宅などの身近な場所で保管し、供養する比較的新しい方法です。この記事では、手元供養の基本的な知識から具体的な流れ、種類やメリット・デメリットまで詳しく解説します。
手元供養とは?歴史や仏壇との違い
手元供養とは、故人の遺骨の全部または一部を、自宅などの身近な場所で保管し、供養する方法のことです。明確な決まりはなく、自由な形で供養できることが特徴です。
この供養方法は2000年代に入ってから徐々に広まり始めました。核家族化や住環境の変化、お墓を継承する人がいないといった社会的な背景から、新しい供養の形として選ばれるようになりました。手元供養という言葉自体は比較的新しいものですが、実は遺骨の一部を持ち帰るという行為自体は古代から行われていました。
弥生時代には土器の中に遺骨を入れて埋葬する「壺棺葬」という方法が一般的で、江戸時代には旅先で亡くなった人の遺骨を持ち帰って供養する「旅支度」という風習もありました。つまり、手元供養は一過性の風潮ではなく、供養の本質的な形のひとつといえるのです。
また、手元供養に法律上の問題はありません。「墓地、埋葬等に関する法律」が禁じているのは、遺骨を土に埋める「埋葬」という行為であり、自宅での安置は法律に抵触しません。遺骨を必ず墓地に納骨しなければならないという決まりはなく、自宅などに安置して供養することもできます。
仏壇との違い
手元供養と仏壇の違いを理解しておくことも大切です。仏壇は、宗派の仏様(ご本尊)を中心に、宗派の掛軸や故人のお位牌をお祀りするものです。
基本的な仏具を置いてお供え物をし、宗派の形式に合わせた供養のスペースを作ります。このように、仏壇は従来の宗教的空間であり、形式を重んじる供養の場といえます。
一方、手元供養は故人の遺骨を中心にお祀りする方法です。供養の形式や揃えるべきものについて決まりがなく、自分らしさを表現できる供養のスペースを作ることができます。インテリアに馴染むモダンなデザインが多く、マンション暮らしや核家族化が進む現代の住環境にも適した、自由な祈りの空間です。
手元供養をするメリット・デメリット
手元供養を検討する際には、メリットとデメリットの両面をしっかりと理解しておくことが重要です。
「故人を身近に感じる安心感」と「納骨後の寂しさの緩和」に焦点を当てながら、詳しく見ていきましょう。
手元供養のメリット
手元供養には、故人を身近に感じられることをはじめ、経済的な負担の軽減や供養の自由度など、さまざまなメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。
故人を身近に感じられる安心感
手元供養の最大のメリットは、故人をいつでも身近に感じられることです。遺骨をそばに置くことで、故人に見守られているような精神的な安心感を得ることができます。大切な人を亡くしたことによる深い喪失感や悲しみは、簡単には癒えません。
しかし、手元供養を選ぶことで、故人との心のつながりを保ち続けることができます。毎日手を合わせたり、語りかけたりすることで、グリーフケアとしての効果も期待できます。お墓が遠方にあってなかなかお墓参りに行けない方でも、自宅でいつでも供養できるのも大きな魅力です。
経済・身体的な負担軽減
お墓を新たに設ける場合と比較して、経済的な負担を大幅に抑えることができます。
また、お墓が遠方にある場合、お墓参りに行くための時間や交通費、体力も必要になります。高齢になると、お墓参り自体が身体的な負担となることも少なくありません。手元供養なら、そうした負担から解放され、自分のペースで供養を続けることができます。
供養の選択肢が増える
手元供養は、宗教や従来の形式に縛られない自由な供養方法です。故人や遺族の価値観、死生観に合わせて、自分らしい供養の形を選ぶことができます。
従来の常識にとらわれず、現代のライフスタイルに合わせた供養ができることは、多様性が尊重される現代社会において、大きな意義があるといえるでしょう。
手元供養のデメリット
手元供養にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることで、安心して手元供養を続けることができます。
周囲から理解されない場合がある
手元供養は比較的新しい供養方法のため、とくに年配の親族などから理解を得られない場合があります。「遺骨を分けるのは縁起が悪い」「きちんとお墓に入れないと成仏できない」といった考えを持つ方も、少なくありません。
こうした誤解や反対を避けるためには、手元供養が法律上も宗教上も問題ないことを丁寧に説明し、わだかまりが残らないよう家族や親族との話し合いを十分に行うことが重要です。
長期管理の問題
遺骨の管理が個人や家族に委ねられるため、引っ越しの際の移動や、将来的に次世代に管理を引き継ぐ可能性があります。
ご自身で遺骨を管理できなくなったときにどうするか、あらかじめ考えておく必要があります。遺骨は自由に処分できないため、この点を曖昧にしたままにしておくと、残された方に大きな負担をかけてしまうことになります。
保管場所の問題
遺骨の劣化を防ぐためには、適切な保管場所を選ぶ必要があります。カビが生えにくい環境を維持することが重要で、具体的には以下の点に注意が必要です。
直射日光を避け、湿度や温度の高い場所(水回りやクローゼット)は避けましょう。また、結露が発生しやすいエアコンの風が直接当たる場所も避けるべきです。風通しのよい場所を選び、必要に応じて防湿剤を使用することをおすすめします。
紛失する可能性がある
手元供養品は小型で持ち運びやすいため、紛失や破損のリスクがあります。とくに遺骨ペンダントの場合、鎖が切れてしまったり、バッグごと紛失してしまったりする可能性があります。
地震などの災害時にも注意が必要です。保管方法を慎重に検討し、大切に扱うことを心がけましょう。
手元供養の種類
手元供養品には、故人のイメージやライフスタイルに合わせて選べる多様なデザインと機能があります。大きく分けると「身につけるタイプ」と「自宅に置いておくタイプ」に分類できます。
ペンダント
遺骨ペンダントは、本体の内部に空洞(インナーポケット)があり、少量の遺骨を納めることができるアクセサリーです。常に故人を身近に感じたい方に人気があります。
素材も多様で、プラチナ、ゴールド、シルバー、ステンレスなど、予算や好みに合わせて選ぶことができます。デザインも豊富で、一見して遺骨ペンダントとはわからないシンプルなものから、故人を偲ぶモチーフが施されたものまで、さまざまな選択肢があります。
装いを選ばず、ずっと身につけていられるという点で、日常的に故人を感じたい方に適しています。
リング
指輪の内側に遺骨を納められるタイプで、日常になじみやすく、性別や年齢を問わず多くの方に選ばれています。「つながる」「とぎれることのない」という指輪の形が持つ意味が、永遠の想いを指元に感じられるという点で支持されています。
ペンダントは普段身につけないという方でも、リングなら気軽につけられることから、選択肢として検討される方が多いアイテムです。
ブレスレット
手元でいつでも目にできるブレスレットタイプの手元供養品は、念珠タイプ、金属製、革製などデザインが豊富です。着脱することで、気持ちに合わせた使い方ができます。
さりげなく、でも確かに寄り添ってくれる存在として、故人を常に目に留めることができる点が特徴です。
オブジェ
インテリアに溶け込むデザインのオブジェタイプは、遺骨を納める機能を持ちながら、花器やぬいぐるみ、人形などの形をしています。一見して遺骨であることがわからないため、来客時にも自然に飾っておくことができます。
可愛らしい見た目のものは、明るい気持ちで故人を偲ぶことができると、女性やお子様から人気があります。リビングや寝室など、生活空間に自然に馴染ませながら、大切な方を身近に感じることができる手元供養品です。
小型の仏壇
手元供養品を安置するステージや飾り台として機能し、仏壇よりも省スペースでモダンなデザインが多いのが特徴です。ミニ骨壺や仏具を組み合わせることで、自宅の一角に祈りの空間を設けることができます。
現代のインテリアに馴染むデザインが豊富で、マンションやアパートでも設置しやすい点が魅力です。お仏壇を置くスペースはないけれど、しっかりと供養の場を設けたいという方におすすめです。
ミニ骨壺
遺骨の一部を収め、自宅で保管できるコンパクトな大きさの器です。限られたスペースにも保管することができ、種類によっては旅行に持っていくこともできます。
素材は真鍮、ガラス、陶磁器、木などさまざまで、デザイン性が高くインテリアに合わせて選べる多様性があります。故人が好きだった色やモチーフを選ぶこともできます。
また、キーホルダーやカプセルタイプなど、持ち運びしやすい形状のものもあります。インテリア用品として自然と部屋に溶け込むデザインが多く、日々の暮らしの中で故人を感じることができます。
手元供養をする流れ
手元供養を始める際の具体的な流れを、順を追って解説します。流れをしっかりと理解し、準備を進めることで、後のトラブルを避け、安心して手元供養を続けることができます。
1.家族等と相談する
手元供養を始める前に、まず家族や親族との相談が最も重要です。
手元供養は比較的新しい供養方法のため、親族間で意見が分かれる可能性があります。とくに年配の方の中には、従来の供養方法を重んじる方もいらっしゃいます。わだかまりが残らないよう丁寧な説明を行うことが大切です。
手元供養が法律上も宗教上も問題ないこと、そしてご自身がなぜ手元供養を選びたいのかという想いを、誠実に伝えましょう。親族間のトラブルを未然に防ぐことが、長期的に安心して供養を続けるための第一歩となります。
2.墓地・寺院と相談する
すでに納骨済みの遺骨を分骨する場合や、宗派によっては特定の儀式や祈祷が必要な場合があるため、事前に墓地や寺院に確認することが重要です。
お墓がある場合は、管理者や住職に手元供養の意向を伝え、手続きについて相談しましょう。分骨証明書が必要かどうかも、この段階で確認しておくとスムーズです。
3.手元供養品を決める
納めたい遺骨の量や身につけたいか自宅に置きたいか、といったライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。故人が好きだった色や花、モチーフなどを考慮することで、より思い入れのある手元供養品を選ぶことができます。
長く愛用できるよう、予算内で質の良いものを選ぶことをおすすめします。デザイン重視なのか、機能性重視なのかを明確にすることで、選択肢を絞りやすくなります。
4.手元供養品を注文する
手元供養品は、葬儀社や仏壇仏具店、インターネットなどで購入できます。
とくに特注品は納入までに時間がかかる場合があるため、四十九日の法要前に手元供養を始めたい場合は、早めの準備を心がけましょう。名入れサービスなどを利用する場合も、余裕を持ったスケジュールで注文することが大切です。
5.設置場所を決める
自宅のどこに置くかは自由ですが、日々お参りしやすいリビングや寝室など、生活の中心となる場所が適しています。お仏壇がある場合は、その近くに安置するのもよいでしょう。
故人を自然に思い出せる場所、手を合わせやすい場所を選ぶことが、継続的な供養につながります。
6.管理をする
長期的な安心感を提供するため、適切な管理が必要です。
カビ対策として、直射日光を避け湿気の少ない場所に保管しましょう。湿気対策として防湿剤の使用や密閉できる容器の選択も有効です。
定期的な清掃を行い、遺骨の状態を確認することも大切です。手袋を着用するか、手の水気をしっかりと拭き取ってから触れるようにしましょう。適切な環境で保管することで、長期にわたって安心して供養を続けることができます。
7.手元供養の見直しをする
将来、管理が難しくなった場合や心境の変化があった際に、遺骨を新しいお墓や納骨堂、永代供養墓へ移す選択肢があることを知っておくことは重要です。
長期的な管理の不安は、あらかじめ選択肢を知っておくことで解消できます。ご自身にもしものことがあったときに、残された方がどうすればよいか迷わないよう、意思を伝えておくことも大切です。
メモリードのお葬式では、葬儀後のサポートとして、墓地・墓石のご相談や終活サポートも承っております。手元供養の見直しや、将来的な不安についても、お気軽にご相談ください。
全骨と分骨の違い
手元供養を始める際、遺骨のすべてを保管するか、一部だけを残すかという選択があります。それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
全骨
全骨とは、火葬後の遺骨のすべてを自宅などで保管する方法です。一般的な骨壺は6〜7寸のサイズがあり、そのまま自宅に安置するには場所を取ってしまいます。また、手元供養品の多くは小型であるため、全骨を納めることは困難です。
そこで、遺骨を粉末状に加工する「粉骨」という方法があります。粉骨により、体積を約3分の1から5分の1に減らすことができ、より小さな容器に納めることが可能になります。
全骨を自宅で保管したい場合には、粉骨を検討されることをおすすめします。また、全骨を収納できる仏壇もあります。お墓を購入するよりもリーズナブルで、お墓参りやお墓掃除も不要となり、毎日好きなときに故人を偲ぶことができます。
分骨
分骨とは、遺骨の一部を手元に残し、残りを墓地などに納骨する方法です。
身につけるアクセサリーやミニ骨壺での供養に適しており、万が一紛失してしまった場合でも、お墓に遺骨があるという安心感があります。
分骨する場合、遺骨には所有者が決まっているため、所有者をはじめとした親族の了承を得ることが必要です。どのくらいの量の遺骨を手元供養にするのかも、家族で話し合って決めましょう。
分骨証明書について
分骨自体に許可は不要ですが、分骨した遺骨を将来的にお墓に戻す際に、分骨証明書が必要になります。
分骨証明書は、納骨前であれば火葬業者や火葬場、納骨後であれば墓地・霊園の管理者に依頼して発行してもらいます。しかし、火葬時に発行してもらうのが最も簡単で確実です。
あらかじめ分骨することが決まっていれば、葬儀社が手続きを代行してくれます。将来的に納骨する可能性がある場合は、早めに取得しておくことをおすすめします。
なお、手元供養のみで納骨の予定がない場合、分骨証明書は必ずしも必要ではありません。ただし、後々納骨することになった際に必要となるため、取得しておくと安心です。
墓地、埋葬等に関する法律では、遺骨を土に埋める「埋葬」には許可が必要とされていますが、手元供養のように自宅で保管する場合は埋葬には該当しないため、特別な手続きは不要です。
出典:e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/20201225_502M60000100208)
残った遺骨の供養方法
手元供養品に納める遺骨は少量のため、残った遺骨をどのように供養するかも重要です。現実的な選択肢をご紹介します。
お墓に入れる
最も一般的な方法として、墓地への納骨があります。手元供養品を紛失した場合でも、遺骨がお墓に納められているという安心感があります。
遠方にお墓がある方でも、大部分はお墓に納骨し、一部を手元供養とすることで、両方のメリットが得られます。先祖代々のお墓がある場合、そこに納骨することで故人が先祖とともに眠ることができます。
納骨堂や永代供養墓に入れる
永代供養墓は、お墓の承継者がいない場合や費用に問題がある場合に、寺院や霊園が遺骨を永代にわたって管理・供養する形式です。
永代供養墓には、ほかの方の遺骨と一緒になる合祀型と、区画が分かれている個別型など、多様な形式があります。合祀型は比較的費用を抑えられますが、一度納骨すると遺骨の返還はできません。個別型は一定期間は個別に保管され、その後合祀されるケースが多いです。
どちらの形式が適しているかは、予算や供養の考え方によって異なるため、事前に内容をよく確認しましょう。
メモリードのお葬式では、納骨堂や永代供養墓についても詳しくご案内しております。手元供養と合わせて、最適な供養方法をご提案いたしますので、ぜひご相談ください。
樹木葬にする
樹木葬は、樹木を墓標とする供養方法で、自然葬の一種です。自然に還りたいという想いを持つ方に選ばれています。
樹木葬には主に3つの種類があります。合祀型は、共同の樹木の下にほかの方の遺骨と一緒に埋葬される形式で、最も費用を抑えられます。集合型は、共同の樹木を使用しますが、埋葬場所はほかの方と区別される形式で、価格は中間的です。個別型は、故人ごとに樹木を植え、埋葬場所も区別される形式で、最も高額になります。
樹木葬の多くは永代供養がセットになっており、墓石や土地が必要ないため、従来のお墓よりも費用を抑えることができます。
散骨をする
散骨は、遺骨を粉末状(パウダー状)にして海や山に撒く方法です。
散骨を行う前には、遺骨を2ミリ以下に粉砕する粉骨が必要です。大部分は散骨し、一部を手元供養とする組み合わせも人気があります。
注意点として、散骨に特別な手続きは不要ですが、自治体による場所や方法の制限があります。トラブルを避けるために、散骨できる場所を事前に確認し、専門業者に依頼することが望ましいです。
また、法律では「墓地以外の区域に埋葬してはいけない」と定められているため、粉骨されていない遺骨に自然と土がかかってしまった場合も埋葬とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
手元供養に宗教は関係ない?
手元供養は「故人を思う気持ち」を中心とした、宗教に縛られない自由な供養方法です。
仏教、キリスト教、神道など、特定の宗教でも、また無宗教であっても、手元供養を行うことができます。宗教や宗派によっては、細かい形式や決まりがある場合もありますが、手元供養には明確な決まりがないため、ご自身のライフスタイルや考え方に合った供養の形を選べます。
無宗教の方でも、宗教に従った形(仏事・法要)のどちらでも選択できるという柔軟性が、手元供養の大きな魅力です。形式や従来の常識にとらわれず、ご自身と故人にとって最も心地よい供養の形を見つけることが大切です。
まとめ
手元供養は、故人を身近に感じながら悲しみを和らげるための新しい供養の形です。お墓への納骨だけでなく、ご自身のライフスタイルや想いに合わせた供養の選択肢として、多くの方に選ばれています。
手元供養の種類は多様で、ペンダントやリングなどのアクセサリータイプから、ミニ骨壺やミニ仏壇まで、幅広い選択肢があります。故人を身近に感じられる安心感、経済的・身体的な負担の軽減、供養の自由度の高さなど、多くのメリットがある一方で、周囲の理解を得ることや長期的な管理の課題もあります。
大切なのは、ご自身の気持ちを大切にし、家族や親族とよく話し合いながら、最適な方法を選ぶことです。手元供養は葬儀後の供養の一部であり、将来的な見直しも含めて、柔軟に考えていくことが重要です。
メモリードのお葬式では、手元供養に関するご相談をはじめ、法事や仏壇仏具、墓地・墓石、終活サポートなど、トータルでサポートしております。手元供養を検討されている方、将来的な管理に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。皆様が故人を偲び、心穏やかに供養を続けられるよう、私たちがお手伝いいたします。