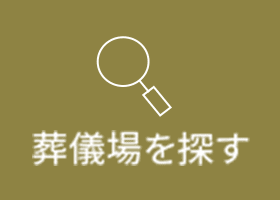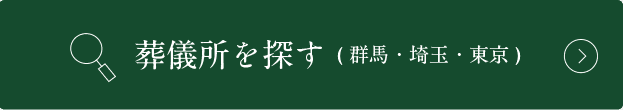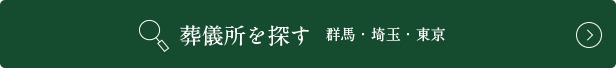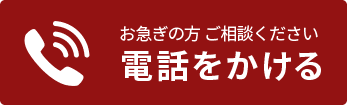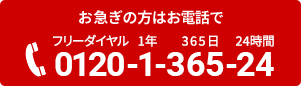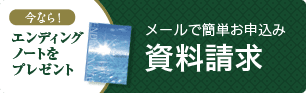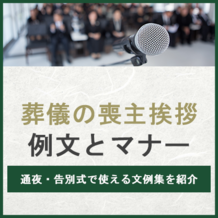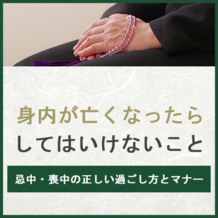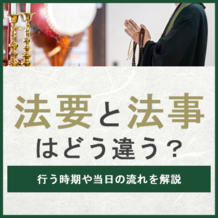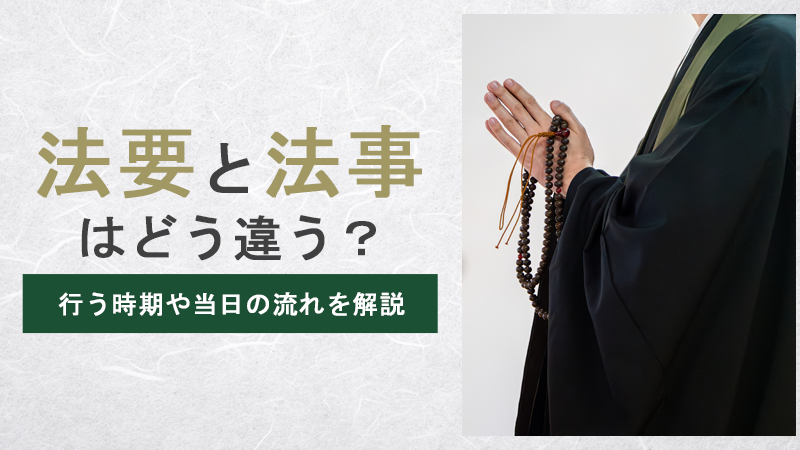
法要とは故人を供養する儀式のことです。法事との違いや種類、準備の流れ、当日のマナーまで初めて施主を務める方向けに詳しく解説します。
初めて施主として法要を執り行う際「法要と法事の違いは?」「いつ、何をすればいいの?」と不安を感じる方は多いものです。この記事では、法要の基本知識から準備の手順、当日の流れまで、初めての方でも安心して執り行えるよう具体的に解説します。
法要とは?法事との違い
法要とは、僧侶による読経や焼香を通じて故人の冥福を祈る仏教の儀式です。「追善供養」とも呼ばれ、この世に残された者が善行を積むことで、故人が極楽浄土へ導かれるよう祈りを捧げます。
仏教では、亡くなってから四十九日間を「中陰」と呼び、故人は7日ごとに生前の行いを審判されるといわれています。遺族は審判がよいものとなるよう、7日ごとに法要を営み故人に善を送るのです。
ただし、宗派により考え方は異なります。多くの宗派で追善供養を行いますが、浄土真宗では「往生即成仏」の考えから追善供養は行わず、阿弥陀如来への感謝や仏法に触れる場として法要を営みます。
法事との違い
法要は僧侶の読経や焼香といった宗教的儀式そのものを指し、法事は法要に加えて会食(お斎)や挨拶などを含めた一連の弔事全体を指します。つまり、法事の中に法要が含まれる関係です。案内状には「○回忌法要」と明記し、会食の有無も記載するのが一般的です。
法要の種類と行う時期
法要には、故人が亡くなってからの経過期間によって、いくつかの種類があります。ここでは、忌日法要、年忌法要、忌明けの法要の3つに分けて、それぞれの特徴と時期を解説します。
忌日法要
忌日法要とは、故人が亡くなった日を1日目として7日ごとに執り行う法要です。主な忌日法要は以下の通りです。
- ・初七日(しょなのか):命日から7日目
- ・二七日(ふたなのか):命日から14日目
- ・三七日(みなのか):命日から21日目
- ・四七日(よなのか):命日から28日目
- ・五七日(いつなのか):命日から35日目
- ・六七日(むなのか):命日から42日目
- ・七七日(四十九日):命日から49日目
- ・百箇日:命日から100日目
現代では、初七日は葬儀当日に繰り上げて行う「繰り上げ法要」が一般的です。四十九日法要は7回目の審判が終わり、故人が極楽浄土へ行けるかが決まる最重要の法要とされます。
この日は「忌明け」と呼ばれ、喪に服していた遺族が日常に戻る節目です。親族や友人を招いて僧侶に読経をあげていただき、会食を催すのが一般的です。四十九日法要では、白木の仮位牌から本位牌に魂を移す「開眼法要」や、納骨を同時に行うことも多くあります。
また、初七日と四十九日以外は、遺族だけで済ませたり、省略する場合もあります。
年忌法要
年忌法要とは、故人の祥月命日に合わせて一定の年ごとに行う法要です。亡くなった日を1回目として数えます。
- ・一周忌:命日から満1年目
- ・三回忌:命日から満2年目(注:「三周忌」ではなく「三回忌」)
- ・七回忌:命日から満6年目
- ・十三回忌:命日から満12年目
- ・十七回忌:命日から満16年目
- ・二十三回忌:命日から満22年目
- ・二十七回忌:命日から満26年目
- ・三十三回忌:命日から満32年目
- ・五十回忌:命日から満49年目
一周忌は、遺族にとって喪が明ける大切な節目です。三回忌は、亡くなった日を1回目と数えて3回目の命日、つまり満2年目に執り行います。三回忌で来世の道が決まる重要な法要とされています。三回忌までは親族以外も招きますが、七回忌以降は規模を縮小し、親族のみで執り行う傾向にあります。
弔い上げは一般的に三十三回忌を区切りとすることが多いですが、地域や宗派により十七回忌や五十回忌で行う場合もあります。菩提寺や親族と相談して決めましょう。
忌明けの法要
四十九日を過ぎた後も、特別な時期に法要を営む習慣があります。初盆(新盆)は、四十九日後に初めて迎えるお盆で、死後初めて故人の魂が現世へ戻る期間とされるため重要視されます。親族や友人を招いて僧侶に読経をあげていただくのが一般的です。
お彼岸は、春分・秋分の日を中日とする前後3日間で、年2回あります。お墓参りをして故人を供養します。納骨法要の時期に決まりはありません。また、お盆とお彼岸に法要を必ず行う必要はなく、お寺と付き合いがある場合は、自宅に招いてお経を上げてもらうとよいでしょう。
四十九日法要と同時に行うことが多いですが、百箇日や初盆、一周忌など遺族の気持ちが落ち着いたタイミングで執り行えます。納骨には埋葬許可証が必要です。
法要前の準備
法要をスムーズに執り行うには、2~3か月前からの計画的な準備が必要です。
| 【2~3か月前】 | 日程と会場の決定 祥月命日または命日近くの土日祝日を選び、菩提寺や会場に早めに連絡します。 会場は菩提寺、自宅、斎場、ホテルなどから選択します。 僧侶への依頼も日程と場所が決まったら早めに連絡しましょう。 |
| 【1か月半前】 | 案内状の発送 日時・場所・会食の有無を明記した案内状を、返信用はがきを添えて郵送します。 返信期限を設定すると、その後の準備がスムーズです。 |
| 【1か月前】 | 参列者の確定と各種手配・会食の手配・引き出物の手配 お祝いを連想させる食材は避けます。 海苔、お茶、お菓子、カタログギフトなどの消えものが一般的です。 |
| 【2~3週間前】 | 供花・供物の手配と席順決定 白菊や百合を中心とした供花を手配し、会食の席順(僧侶が上座、施主が下座)を決めます。 |
| 【1週間前】 | お布施の準備 御車代と御膳料(僧侶が会食に不参加の場合)も用意します。 |
| 【前日】 | 当日の持ち物確認 遺影、位牌、数珠、お布施、引き出物などを準備します。納骨を行う場合は遺骨と埋葬許可証も忘れずにしましょう。 |
会場手配や僧侶の紹介、引き出物の準備など、総合的なサポートを利用すれば準備の負担を軽減できます。メモリードのお葬式では、法要に関する各種サポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。
法要当日の流れ
法要当日は施主が進行役を務めます。三回忌法要を例に、一般的な流れを解説します。
1.僧侶の入場と挨拶
僧侶が入場後、施主は参列者に向けて開式の挨拶をします。「本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。これより故○○の三回忌法要を執り行います」など、簡潔に述べます。参列者の着席順は、僧侶、親族の年長者、施主の順です。
2.読経と焼香を行う
僧侶の読経が始まり、参列者は血縁の近い順に焼香を行います。焼香の作法や回数は宗派により異なるため、自身の宗派に合わせて行いましょう。読経と焼香は1時間程度です。
3.法話を行う
読経後、僧侶から法話があります。仏教の教えや故人の思い出話など、参列者が故人を偲ぶ心温まる時間です。
4.僧侶が退場する
法話終了後、僧侶が退場します。施主はお布施を切手盆に乗せて丁寧にお渡しします。お布施は感謝の気持ちを表すものです。僧侶が会食に不参加の場合は、御車代と御膳料もお渡しします。
5.施主が挨拶して法要を締める
僧侶退場後、施主は参列者への感謝と今後の支援をお願いする挨拶で法要を締めます。会食がある場合はその場所を案内し、ない場合は散会の旨を伝え、引き出物をお渡しします。
6.お墓参りをする
菩提寺での法要やお墓が近くにある場合は、法要後にお墓参りをしましょう。墓石を清め、花や線香を供えて合掌します。納骨を行う場合は埋葬許可証が必要です。
7.会食をする
法要後の会食(お斎)は、故人を偲び参列者が親交を深める時間です。開始時に施主が挨拶し、親族の年長者または故人と親しかった方に献杯(けんぱい)をお願いします。献杯は静かに唱和して杯を口元に運ぶのがマナーです。
会食は精進料理が習わしですが、近年はレストランやケータリングの利用も増えています。ただし、伊勢海老や鯛などお祝いの食材は避けましょう。会食終了時に、施主は引き出物を参列者に手渡します。
法要全体の所要時間は、法要約1時間、会食約2時間で、合計3時間程度が目安です。
まとめ
法要は故人を偲び、遺族や親族が心を通わせる大切な時間です。初めて施主を務める方にとっては、準備や当日の進行に不安を感じることもありますが、種類や時期、準備の流れを理解することで、滞りなく執り行うことができます。
法要の準備には、日程調整、会場手配、僧侶依頼、案内状発送、引き出物手配、お布施の用意など多くの作業がともないます。また、納骨を行う場合は、お墓や納骨堂の手配、墓石への彫刻、納骨法要の依頼なども必要です。
メモリードのお葬式では、法事・法要に関する総合的なアフターサポートを提供しています。会場や僧侶の手配、仏壇・仏具の準備、お墓や墓石のご相談など、施主の負担を軽減するサポート体制を整えております。
初めての法要で不安がある方、準備の手間を省きたい方は、ぜひメモリードのお葬式にご相談ください。故人を偲ぶ大切な時間を、心穏やかに迎えられるよう、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
お困りの際にはぜひお問い合わせください。