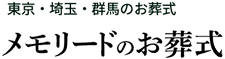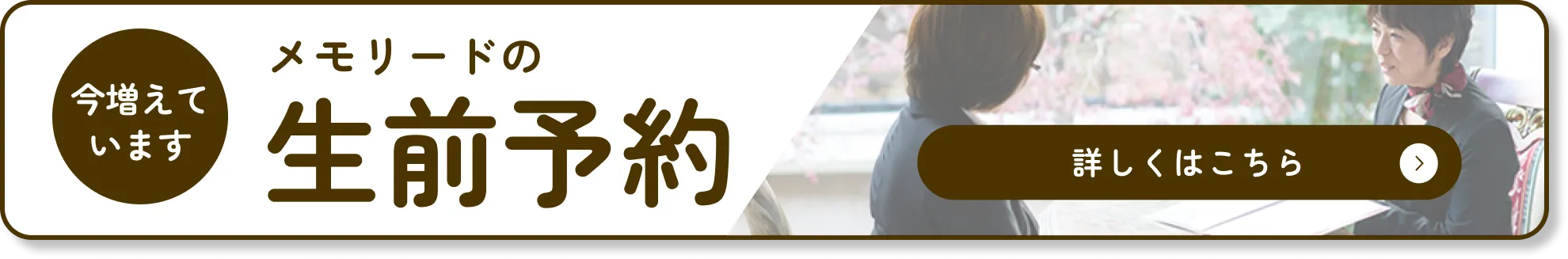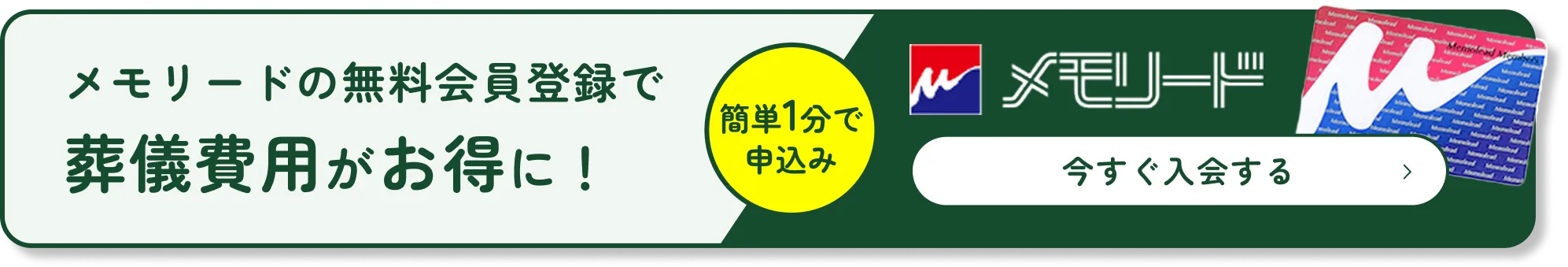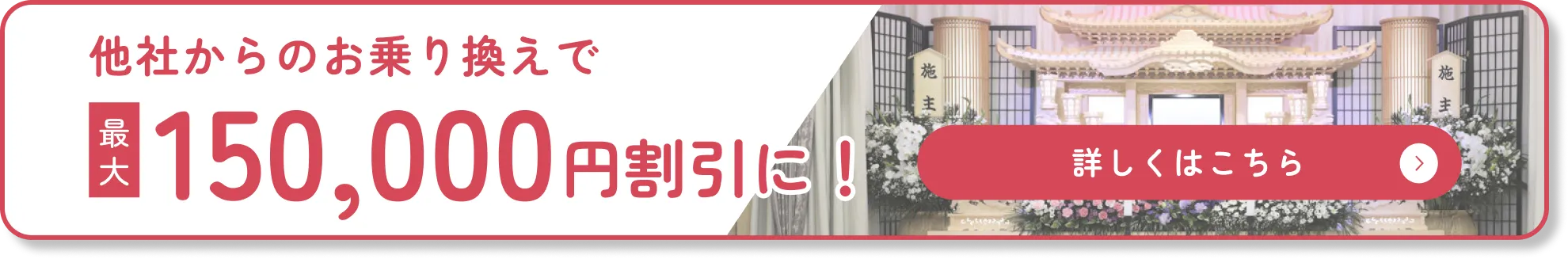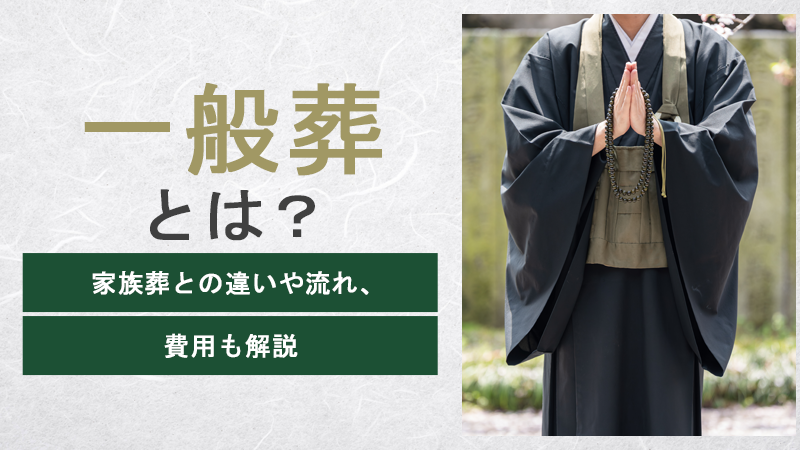
近年、小規模なお葬式が注目される中でも、一般葬は従来通りの葬儀形態として高いニーズを持ち続けています。一般葬は参列者を限定せず、故人と縁のあった多くの方々に見送っていただく、社会的なお別れの意味合いが強い葬儀です。
本記事では、一般葬の特徴、家族葬との違い、具体的な流れ、費用傾向、参列時のマナーなど、故人を心ゆくまで見送るための情報を詳しく解説します。
一般葬とは?
一般葬とは、参列者を限定せず、広く多くの関係者に参列していただく葬儀のことを指します。故人と縁のあった方々に社会的なお別れの機会を提供する意味合いが強く、ご家族だけでなく、友人・知人、会社関係者、近所の方など幅広い層の方々に参列していただく伝統的な葬儀形式です。
通夜、葬儀・告別式という宗教的儀式が二日間にわたって行われるのが一般的で、そのため「二日葬」とも呼ばれる場合があります。参列される多くの方に失礼がないよう、地域独自のしきたりや風習にも配慮し、飲食での接待も行います。
近年、葬儀の多様化やコロナ禍の影響で規模が縮小傾向にありますが、それでも依然として多くの人に見送ってもらいたいというニーズが存在しています。一般葬の形式でも、通夜を行わない一日葬や特定の宗教行事を行わない無宗教葬の形式をとる場合もあり、柔軟性があるのも特徴です。
家族葬との違い

一般葬と家族葬の本質的な違いは、形式そのものよりも誰を対象とした式なのか、どこまで社会的儀礼を意識するかという方向性にあります。参列範囲と社会的対応の幅が、両者を分ける最も重要な要素といえるでしょう。
参列者の範囲
一般葬は「参列者に制限を設けない方式」であり、家族葬は「ご家族が声を掛けた方のみが参加できる」という根本的な相違点があります。
一般葬では、故人と縁のあった方々に広く訃報をお知らせし、参列するかどうかは受け取った方が決めることができます。家族葬では、喪主が参列者を限定し、家族が直接連絡する方のみが参加します。ただし、家族葬であっても親しい友人を数名招くケースは多く、人数だけで家族葬か一般葬かを明確に線引きできない点も覚えておきましょう。
一般葬では新聞への訃報掲載や町内会への通知など、広く知らせる方法が取られるのに対し、家族葬では限られた範囲への個別連絡が中心となります。
香典の有無
一般葬では供物・供花、不祝儀(香典)を受け取ることが多いのに対し、家族葬ではこれらを辞退することが多い傾向にあります。
香典を受け取ることで葬儀費用の一部を賄える可能性がある点が一般葬のメリットのひとつです。一方、家族葬で香典を辞退すると自己負担が大きくなる可能性があります。ただし、家族葬でも香典を受け取ることは可能であり、その場合は香典返しを用意する必要があることもおさえておきましょう。
葬儀の流れ
一般葬が「通夜を行い、その翌日に葬式を行う」という2日間にわたる形式が多くとられるのに対し、家族葬の場合、通夜を行わない「一日葬」や、火葬場でのみのお別れとなる「直葬(火葬式)」のプランが選ばれやすい傾向があります。
もちろん、一般葬であっても一日葬を選ぶことは可能であり、家族葬であっても2日間にわたる葬儀を行うこともできるなど、柔軟な選択肢があることを理解しておくことが大切です。
葬儀に必要な準備
一般葬と家族葬では、葬儀準備の手間と範囲に大きな違いがあります。
家族葬を選ぶ場合はとくに「誰を呼ぶのか、訃報を出すのか、供物や香典を受け取るのか」といった点を事前に決める必要があり、これらが準備内容を大きく左右します。
一般葬では、参列者が多いため、遺影の準備、おもてなし料理の手配、供花・供物の準備、座席や火葬場への同行者の決定、お手伝いの依頼、弔辞の依頼、出棺時の挨拶など、準備事項が多岐にわたります。
こちらの記事では、家族葬について解説しています。 注意点や呼ばない方への対応方法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
一般葬に参列できる範囲
一般葬は参列する方に制限を設けない方式であり、故人やご家族の交流関係の広さに応じて参列者数が大きく変動する可能性があります。
参列者の一例として、故人のご家族、知人・友人、近所にお住まいの方、学校・職場の関係者などが挙げられます。基本的には故人や遺族の関係者であれば、どなたでも参列していただけるのが一般葬の特徴です。
葬儀まで時間がない中で、遺族がご参列いただく方全員に連絡するのは困難なため、各お付き合いの中で、代表者や中心となる方に葬儀の案内を行い、その方から関連の方に連絡していただくとスムーズに進みます。
お別れの場をしっかりお伝えするためやお知らせ漏れを防ぐために、事前に年賀状や携帯電話の電話帳などで、どのような方がいるか把握しておくことも重要です。
一般葬の流れ
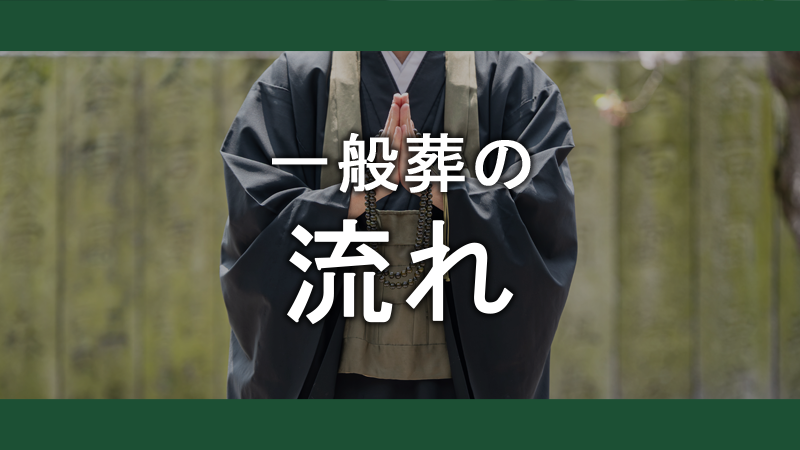
一般葬の流れは、家族葬や一日葬などほかのセレモニーを行う形式のお葬式と大きな違いはありません。ここでは通夜を行う葬儀の形式を例に、具体的な流れを紹介します。
事前相談
ご家族が亡くなる前に葬儀について葬儀社と事前に相談すると、いざというときに慌てることなく対応できます。
無料の事前相談では、葬儀式場、花祭壇、お料理、返礼品など葬儀に関わることを相談・決定でき、その時点での見積もりを出してもらえます。
事前相談には「お金の心配を減らせる」「悲しみの中での混乱を防ぐ」「故人らしさを大切にできる」「家族の絆を深められる」「トラブルを未然に防ぐ」「より良い選択ができる」といった、具体的なメリットがあります。
当日
ご家族が亡くなったら、まずは葬儀社へ連絡します。ほとんどの葬儀社が24時間365日対応しているため、深夜や早朝でも安心です。病院や警察で紹介された葬儀社を断ることも可能ですし、一度搬送をお願いした後でも葬儀社を変更できることも覚えておきましょう。
死亡診断書(死体検案書)を受け取り、役所に提出して火葬許可証を申請する流れが必要です。故人を安置する場所(自宅または安置専用施設)を決定し、防腐処理を行う「安置」を行います。
この時点で、葬儀の内容について葬儀社と打ち合わせを行い、訃報紙を作成します。訃報は故人が逝去したことと葬儀の詳細を記載したお知らせであり、一般葬では広く送ることになります。葬儀社が葬儀場・火葬場の予約を行うのも、この段階です。
翌日
故人のお身体を清めてお棺に納める「納棺」の儀式を行います。通常は葬儀社のスタッフが丁寧に行いますが、ご家族も立ち会うことができます。
お通夜は、告別式の前夜に行う儀式であり、故人が肉体とともに過ごす最後の夜です。一般的な流れとして、参列者集合、お坊さんによる読経、参列者による焼香、お坊さんの説教、喪主の挨拶、通夜振る舞いが行われます。通夜振る舞いでは、参列者に料理をお出しし、故人の思い出話を共有する貴重な時間となります。
翌々日
葬儀・告別式は、火葬当日の火葬前に行います。お坊さんによる読経、参列者による焼香、弔電の紹介、喪主の挨拶などが行われ、お通夜があまり宗教儀式にとらわれないのに対し、葬儀・告別式は宗教儀式に則って行うのが一般的です。
出棺では、故人が納められたお棺を葬儀場から出して火葬場に運びます。故人と顔を見られる最後の瞬間であり、お棺に花や手紙を入れることがあります。お棺に入れられるもの(おもちゃ、ぬいぐるみ、写真、手紙など)と入れられないもの(アクセサリー、缶・瓶、硬貨・紙幣など)があるため、判断に迷った場合は葬儀社に相談しましょう。
火葬の時間は個人差がありますが、約1時間ほどです。火葬中に精進落としなどをいただきながら、喪主・ご家族・参列者で故人の思い出話をする貴重な時間となります。火葬終了後、遺骨を骨壺に収める「収骨」を行い、葬儀が終了します。
精進落としは、葬儀後に参列した方と食べる食事で、最近は簡略化されたり、お弁当として持ち帰り形式になったりすることもあります。
一般葬のメリット
一般葬には、参列者を招くことで得られる安心感や社会的なつながりなど、家族葬にはない利点があります。ここでは、一般葬ならではのメリットについて具体的に見ていきましょう。
故人とお別れしたいという人を呼べる
家族葬のように呼ぶ人数が限定されないため、故人と最期のお別れをしたいと願う多くの方々の気持ちに応えられることが最大のメリットです。
故人の人生において大切な関係を築いてきた方々が、一堂に会してお別れできる機会を提供できるのは、一般葬ならではといえるでしょう。参列者から故人の新たな一面を知る機会もあり、遺族や親族が知らなかった故人の交友関係や、思い出話、エピソードを参列者から聞くことができる貴重な場にもなります。
親族から反対が起こりにくい
一般葬は古くから行われてきた伝統的な葬儀形式であるため、家族葬や一日葬といった新しい形式と比べて、伝統を重んじる親族や菩提寺からの反対意見が出にくいです。
周囲からの賛同が得られやすい点も、喪主や遺族にとって精神的な負担を軽減する要因となります。地域の風習や慣習に沿った形で葬儀を進められるため、後から「あの時ああしておけば良かった」という後悔も少なくなります。
後日の弔問の対応が少なくなる
葬儀の場で多くの人に一度にお別れを済ませてもらえるため、葬儀後に自宅を訪れる弔問客の数を減らせます。これにより、喪主や遺族の精神的・肉体的・時間的な負担を軽減できることは大きなメリットです。
家族葬などの小規模な葬儀では、知らせを受けなかった方から後日弔問や香典の申し出があり、対応に追われる可能性が高くなります。一般葬であれば、そのような個別対応の必要性を大幅に減らすことができ、遺族は落ち着いて故人を偲ぶ時間を確保できます。
また、生前お世話になった方々に遺族から感謝の気持ちを伝えることができる貴重な機会でもあります。
一般葬のデメリット
一般葬には大きな安心感やつながりを得られる一方で、準備や費用、遺族への負担といった注意点もあります。ここでは、一般葬を選ぶ際に知っておきたいデメリットについて解説します。
参列者の対応に追われる場合がある
親族以外にも多くの参列者が来るため、喪主やご家族は挨拶や応対に時間を割かなければならず「故人の側から一瞬たりとも離れたくない」「気の置けない親族とだけ感情を共有したい」と考える場合には、これが大きなデメリットとなることがあります。
結果として故人をゆっくり偲ぶ時間が少なくなる可能性もあり、2日間にわたる儀式で、故人と関係が深い人ほど悲しみを抑えたまま列席する必要があるため、精神的・肉体的な負担が大きくなることも考慮すべき点です。
費用が高くなりやすい
一般葬は規模が大きくなる傾向があるため、大きなホール使用料、祭壇、装花、スタッフの人件費、通夜振る舞いなどの費用がかさみやすいのが実情です。
ただし、香典収入があるため、自己負担が軽減される可能性もあります。また、参列者側にも1〜2日の時間的拘束や、香典による金銭的な負担、長時間の着座や乳幼児連れの参列による負担など、相応の負担をかけてしまう点も配慮すべきデメリットといえるでしょう。
一般葬が向いている場合
故人を「たくさんの人に見送ってもらいたい」という意向がある場合に、一般葬は最適な選択となります。
故人の交友関係が広かった場合、とくに多趣味であったり、自治会などで役員を務めていた、近所付き合いが深かった故人の場合、葬儀への参列を希望する方が多くなるため、一般葬が選ばれることが多いです。
故人が若くしてお亡くなりになられた場合も、仕事関係者や学校関係者など、多くの弔問客が見込まれるため、一般葬を選択される遺族が多い傾向にあります。
故人や喪主が社会的地位のある役職などについている場合、参列者への配慮や社会的な役割を全うしたいという責任感に応えるためにも一般葬が適しています。
親族の中に伝統や宗教儀礼を重んじる方がいる場合、地域の風習に沿って葬儀を行いたい場合や、古くからのお坊さんや菩提寺がある場合も、一般葬を選ぶのが望ましいとされます。
火葬式・直葬・家族葬だと「私だけ呼ばれなかった」というトラブルに発展する可能性もあるため、これらを避けたいケースでは一般葬が良い選択肢となるでしょう。
一般葬を行う際の注意点
一般葬は規模が大きく、多くの人が関わるため、事前の準備や進行において押さえておくべきポイントがあります。ここでは、一般葬を円滑に進めるための注意点を紹介します。
参列者を事前に確認しておく
一般葬では参列者が多く見込まれるため、ご家族や喪主がどなたをお呼びしたいのか、どなたにお別れしていただきたいのかをあらかじめ考えて共有しておくと安心です。
喪主は自分が参列者にお礼を言う立場になるという自覚が必要で、参列者への挨拶はもちろん、通夜振る舞いや香典返しの手配などが必要になることを理解しておきましょう。
香典のマナーに気をつける
香典辞退の有無の確認は重要です。訃報に香典・供花・供物辞退の旨が書かれていれば、持参するのは失礼にあたります。
香典の一般的な相場は、故人との関係性に応じて異なります。親であれば5〜10万円、祖父母・きょうだいなら1〜5万円、おじ・おば・その他の親戚なら1〜3万円、会社の上司なら5,000円〜1万円、友人なら5,000円〜1万円が目安です。地域や本人の年齢によって相場が異なる場合があることも覚えておきましょう。
不祝儀袋の選び方と書き方では「不祝儀袋」に入れ、宗派に関係なく使える「御霊前」が一般的な表書きです。キリスト教式では「御花料」「献花料」神式では「御玉串料」無宗教では「御花料」「御霊前」と書きます。薄墨の筆ペンを使って書くのがマナーであり、ボールペンなどは避け、袋の表下半分にフルネームで記載します。
お札の入れ方にも配慮が必要です。新札ではない方がよいとされており、新札しかない場合は折り目を入れます。袋の中の封筒を裏にしてお札を出したときに、肖像画が下に見えるように入れるのが一般的です。
持ち運び方と渡し方では「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる専用の袋に入れて持ち運び、記帳時に受付の方に渡し、その際に小さな声で「この度はご愁傷様です」と伝えるのがマナーです。
供花のマナーに気をつける
供花は故人の祭壇に供える花で、故人の霊を慰め、遺族に弔意を示す目的があります。「きょうか」または「くげ」と読みます。
送るタイミングは、通夜が執り行われる前に届いているのが理想で、遅くとも通夜が始まる3時間前を期限とします。間に合わない場合は葬儀に間に合うように手配するか、故人の自宅に届ける方法もありますが、その際は遺族に確認し日時指定することが丁寧です。
花の種類と色調は、基本的には白色を基調に、菊、百合、胡蝶蘭などが用いられます。近年は故人の好みも尊重されますが、式場の雰囲気を統一するため決められた選択肢から選ぶ傾向が強くなっています。毒性や香りの強い花を避けることも重要です。
札名の書き方では「芳名名札(ほうめいなふだ)」と呼ばれる立札に送り主を記載します。個人(フルネーム)、夫婦(連名)、子ども/兄弟/親戚(「〇〇一同」または連名)、友人(「友人一同」または連名)、法人・会社(正式名称、部署名、役職名)の形式があります。
注文方法は、葬儀社・葬儀会場、花屋、インターネットの3つの方法があります。どの注文方法を選ぶ場合でも、必ず事前に葬儀を執り行う葬儀社に確認をとることが重要です。
供花の相場金額は、1基7,500円〜15,000円、1対(2基)15,000円〜30,000円が目安です。相場と大幅に差があると遺族に気を遣わせるため、適切な金額を選ぶことが大切です。
服装のマナーに気をつける
一般葬だからといって特別なマナーはなく、一般的な喪服で問題ありません。
喪主・家族の服装は、正喪服もしくは準喪服を着用し、略喪服は避けるべきです。
参列者の服装(男性)は、つやのないダークスーツに黒のネクタイを着用します。靴やかばんは華美な装飾のない、暗い色のものを選びましょう。
参列者の服装(女性)は、つやのないダークスーツかワンピースもしくはアンサンブルを着用します。かばんは華美な装飾がなく、暗い色のものが好ましく、靴は大きな音のなるピンヒールなどを避け、高さの低いものにします。
アクセサリーは結婚指輪以外の指輪は着用せず、ネイルは時間があれば外します。耳飾りは一粒のパールのみで揺れるような垂れ下がるものは避け、首飾りはパールの一連のものは着用しても問題ありません。
まとめ
一般葬は、小規模な葬儀が一般化した現代でも、従来通りの形式として依然として高いニーズを持つ葬儀形態です。参列者制限なし、2日間形式という主な特徴があり、家族葬との違いは参列者の限定性にあります。
一般葬の主なメリットとして、多くの人に見送ってもらえる、親族からの賛同が得やすい、後日の弔問対応の負担軽減、故人の新たな一面を知れる機会が挙げられます。一方、デメリットとして費用がかさむ傾向、遺族の負担がありますが、これらのデメリットは考え方次第で軽減でき、充実感・達成感につながることもあります。
メモリードのお葬式では、一級葬祭ディレクターをはじめとする葬儀のプロ集団が、事前相談から葬儀後のアフターサポートまで一貫したサービスを提供しています。24時間365日相談を受け付けており、お客様の状況やご希望に応じて最適なプランをご提案いたします。
映画「おくりびと」の技術指導スタッフが創り上げた質の高いサービスで、故人を心を込めてお見送りいたします。葬儀についてご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。